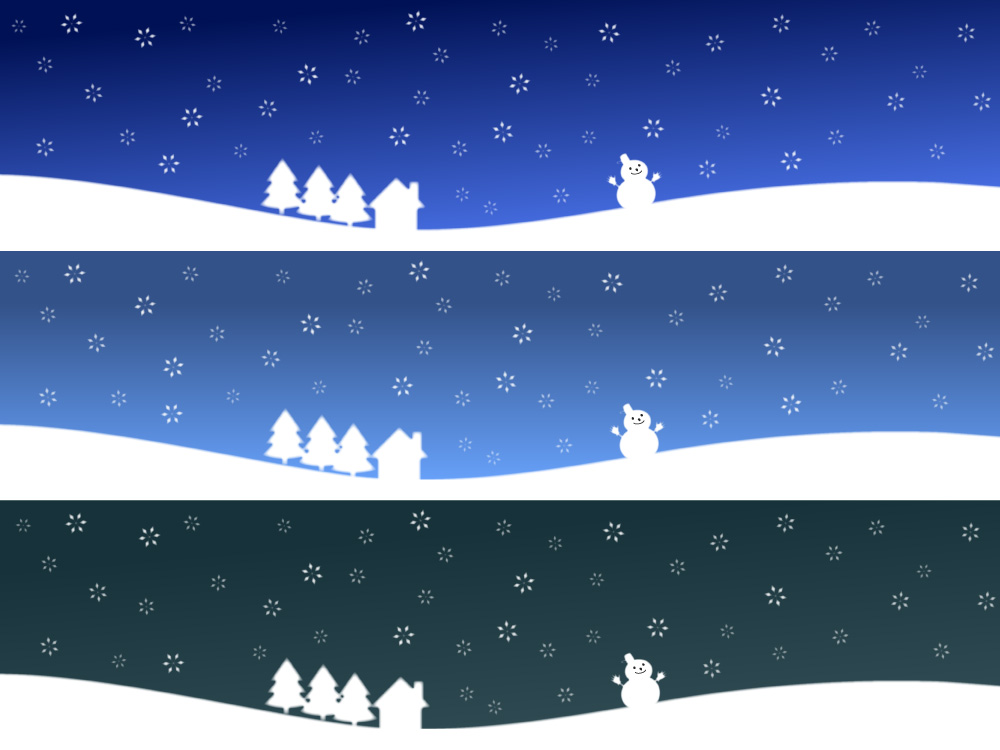共感と精神分析的心理療法 「共依存」にならないためのクライエント/セラピストの関係性とは?
1、はじめに
前回のブログでは、人と人との関係が人の心を治していくことをお伝えしました。そして精神分析的心理療法はこの関係性を作り上げることで、心の辛さや不安や恐怖を治すだけでなく、その人の持っている創造性も開花させることもお伝えしました。
このように私たちはカウンセリングにおいてクライエントとセラピストとの間に安心と信頼の関係を作ることが大切になります。しかし「共依存」という言葉があるように、私たちの人間関係は一見相手のことをおもうように見えても実は相手にも自分にもデメリットが大きい人間関係もあります。
2、新しいこころを作ることとは?
今回はもう少し詳しく治癒と創造性が作り出されるクライエントとセラピストの関係性について説明したいと思います。私たちは精神分析的心理療法を体験することで、本質的・根本的に問題を解決できることをお伝えしました。本質的・根本的というからには、精神分析的心理療法を経験する前と後では私たちの心がまったく別ものになっていることになります。例えば蝶が幼虫からさなぎになり蝶になるには、さなぎの中でそれまでの形を一旦ドロドロに溶かし新たな形に作り直す必要があります。心も同じようにまったく別のものになるにはそれまでの自分の心をドロドロに溶かして新しい心を作る必要があります。
精神分析家W.Rビオンはこのような心のさなぎ体験を、「破滅の恐怖といっていいような解体的な無統合が起きてくる強烈な感覚と不安」として「破局/カタストロフィ」と概念化しました(松木邦裕 精神分析体験:ビオンの宇宙)。すなわち「私たちが心的に一度死んでしまわないと、新しい考えを含んだ自己を構築できません。この心的な死が破局なのです」(前掲 松木)というように、新しい自分、新しい心を作り直す体験は、さなぎの中で一度、比喩的に私たちの心は一度死んでしまわなければならないのです。そしてその体験は破局/カタストロフィと言われるほど怖いものなのです。
ところで「死ぬ前の私」とはどのような私だったのでしょう?私たちは日ごろ、私が言葉を使って何が起きているのかを理解しようとしています。しかし私たちのこころで起きていることは言葉を使っても理解することができないものとビオンは考えました。もっとも私たちはものごころついた時から、言葉を使って考えることを当然と思ってきました。裏返せば言葉を使っても分からないことにとても恐怖を覚えます。そこで私たちはわからないことも言葉を使って分かった気になって安心しようとします。反対にどうしても言葉を使ってわからないことは、「迷信」「非科学的」という烙印を押して安心しています。こうして私たちは世の中にわからないことはないと信じることで安心を得ています。
ではどうすれば、私が言葉を使って理解できないものをつかむことができるのか?現代に生きる私たちは、例えば幽霊を科学的にはこういう根拠や理論で説明できると言ったように、徹底的に言葉を使ってわかろうと、ますます言葉に頼っています。この言葉に頼りすぎることが私たちに大きなストレスを与え、さらなる苦悩を生じさせているのではないでしょうか?そこでビオンは言葉でわからない私たちのこころを言葉を使ってわかろうとすることを止めました。ビオンと同様、この問題を追い求め解決しようとしたのが、古来からの禅や武芸、芸術でした。これらの先人たちは、言葉を使って理解できないものをとらえるために、言葉で理解しようとする「私」を捨て去ることを目指しました。私が考えるから苦悩が生まれる。考える私が苦悩をうむ根源であると考えました。すなわち「死ぬ前の私」とは、言葉を使ってものごとを理解しようとする私なのです。
しかし、言葉を使って考えることを止めることはとても怖いことです。宇宙のただなかに独り放り出されるような絶望感かもしれません。私たちはあまりにも言葉に頼りすぎていたために、言葉を使わない私を捨て去って、その後どのような世界に放り込まれるか想像すらできないのです。でも私たちは言葉で理解できないものをわかる唯一の方法は、言葉で考える「私」を捨て去るしかないのです。先人たちは経験的にそのことをわかっていたのでしょう。「悟りを開く」「達人になる」「奥義を極める」などの言葉は、言葉を使って考える私を捨て去って、未知の世界に入ることができた人を指すことだと思われます。
3、セラピストにとってのさなぎの恐怖
言葉で分かろうとする私を捨て去り、新たな私を作りだす。このことが言葉で理解でいない自分のこころをわかるためには必要になります。しかしその時に生じる破局の恐怖は、新たな自分に生まれ変わるクライエント(患者)はもちろんですが、セラピスト(治療者)にとっても怖いものなのです。なぜなら精神分析的心理療法においての共感とは、クライエントが感じている怖さをセラピストも自分のもののように感じること(専門用語では投影同一視と言います)をいいます。この共感によってセラピストはクライエントが体験している苦悩をまるで自分のことのように追体験できるのです。それゆえクライエントが自身の心を作り替えるときに生じる破局の恐怖を、セラピストも同じように破局の恐怖として体験します。
ところでビオンはクライエント/セラピストの関係を三種類に分類しました。①共存的:第三者の創造と、それら三者に益をもたらす ②共生的:二者だけの利益にとどまる ③寄生的:第三者の創造と、それら三者を破壊する、というものです。(前掲 松木)
カウンセリングを続けていくと一見穏やかな雰囲気に包まれ居心地の良い時間が過ぎていくこともあります。クライエントはセラピストにわかってもらっていると実感でき、セラピストもクライエントの役に立っていると満ち足りた気分になっているでしょう。しかしそのような状態は②の共生的な状況かもしれません。クライエントの破局の恐怖を共感としてわが身のように感じるセラピストは、クライエントが無意識に恐れている、新しい自分になるために生じる破局の恐怖を感じとり、破局の触れることを恐れているかもしれません。セラピストが触れることを怖がっているなら同じようにクライエントも破局の恐怖を避けるでしょう。一見穏やかな状況は新しい心を作るために通らざるを得ない破局の恐怖を、セラピストとクライエントが暗黙の共謀によって避けていることから生じている可能性もあるのです。
新しい心を私たちが作っていくためには破局の恐怖を通り抜けることが必要になります。
カウンセリングを希望される方々は、カウンセリングについて穏やかな癒しをイメージされるかもしれません。この穏やかな癒しのイメージはカウンセリングの大事な要素であることは間違いありません。しかし新しい心を私たちが作っていく段階に入っていったとき、すなわちカウンセリングが新たな創造性を作り上げるという①共存的な状況にあるとき、穏やかな癒しのイメージとは異なる破局の恐怖をセラピストもクライエントも乗り越えていくことが要求されるのです。
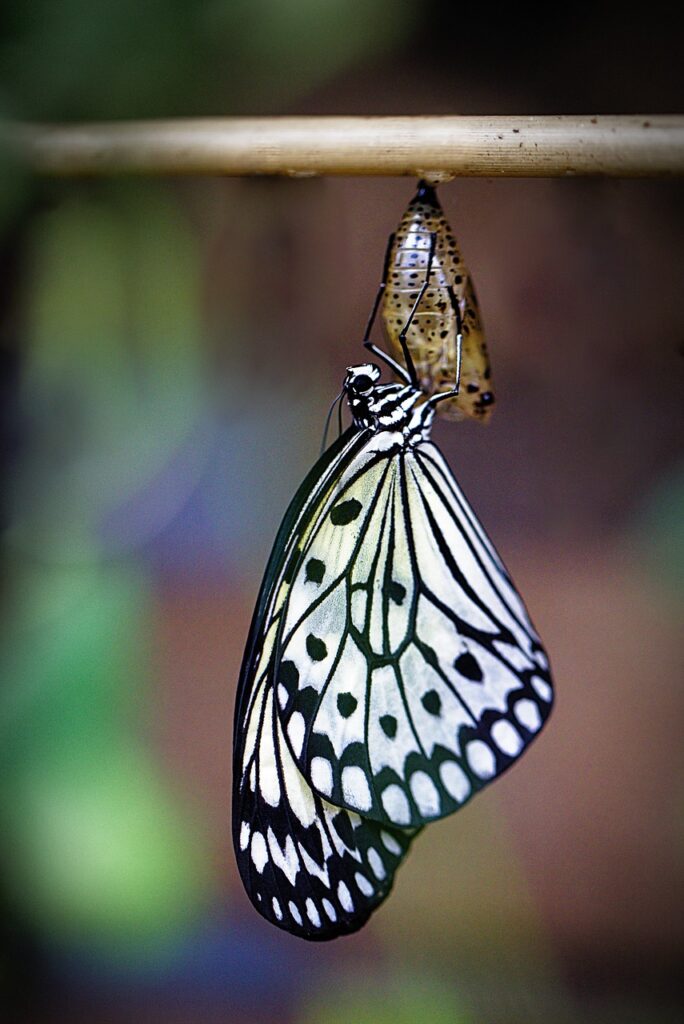
4、セラピストの経験・訓練
ビオンは「負の能力」という概念も提唱しています。セラピストも①共存的状況にカウンセリングが置かれる時に、クライエントが新しい自分に向かうとき、クライエントと同じ破局の恐怖を体験していることはお伝えしました。この時セラピストもその恐怖ゆえに破局を避け、②共生的、③寄生的なカウンセリングへの誘惑に駆られることがあります。この誘惑に耐える力、「負の能力」がセラピストには求められます。セラピストが経験を積みそこから学ぶこと、あるいは訓練や勉強が必要なのは、ひとえに「負の能力」によってクライエントとともに破局の恐怖を乗り越えていくためであると、私は考えています。この点で精神分析的心理療法にとって一番大切な要素は破局の恐怖に立ち向かい乗り越えるための「勇気」かもしれません。もっともこの乗り越える勇気を得るためには、それまでのセラピストがクライエントに寄り添い共感することで、クライエントの信頼を得ることが必要になります。クライエントの信頼があってこそ、クライエントはセラピストと共にこの破局の恐怖に耐え乗り越え、新たな心を創り上げることができるのです。
5、まとめ
今回は、私たちが新しい心を作っていくためには破局の恐怖を乗り越えることが必要になるとお伝えしました。ただカウンセリングを始めていきなり破局に直面するわけではありません。まずはクライエントがセラピストを信頼できるように、セラピストは丁寧にクライエントの不安に寄り添います。またクライエントが破局を恐れる理由もその方独自のものです。セラピストはここでも丁寧に破局に臨めないクライエントの不安に寄り添います。クライエントの様々な不安にセラピストが寄り添い、クライエントが信頼と安心を得られたと感じられたときに、破局が自然と訪れるのです。逆説的な進み方ですが、破局という恐怖は、クライエントが安全を確信したときに訪れると言っていいでしょう。そのためにセラピストはクライエントの信頼を得るように寄り添うことが求められます。