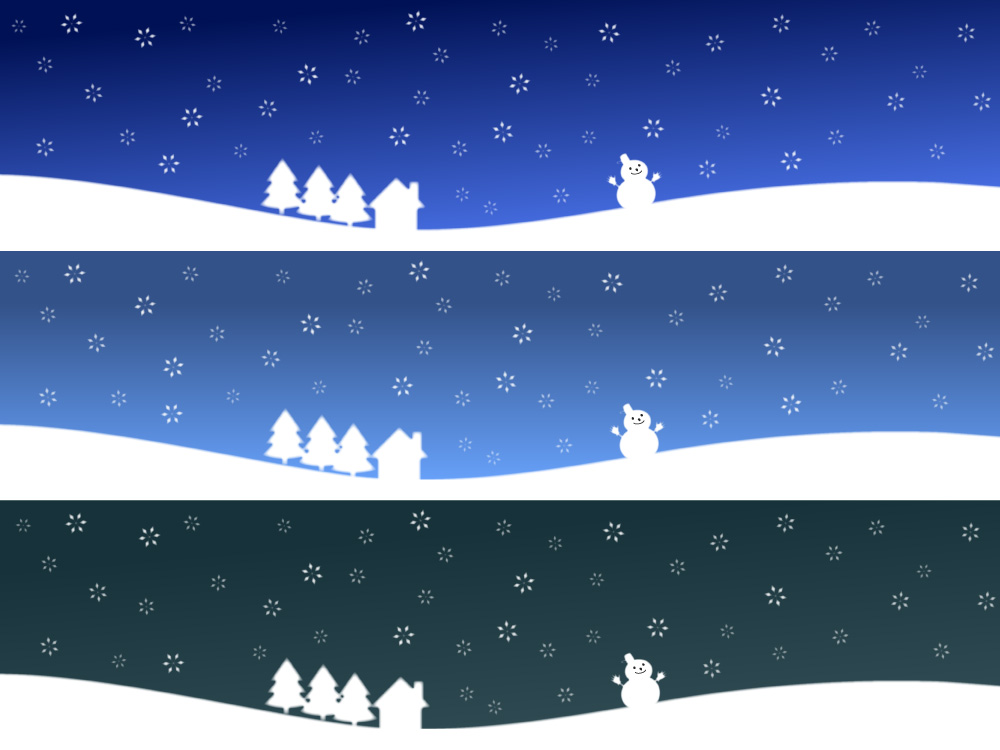個人と集団をシステムという視点で捉え、こころの健康を回復・維持することを考える。
1 はじめに
私たちがストレスを感じたり不安に思ったりと、こころが辛く感じる多くの場合に、人間関係が関わっていると感じていらっしゃる方々も多いでしょう。人とのかかわりは私たちを勇気づけ喜びを与えてくれる一方で、こころを辛くする厄介な面もあります。
今回はこの人間関係を個人と集団のシステムという視点で見ることで、人間関係から生じるストレスについて考えてみたいと思います。
2 私たちは人と人との関係性で生きている。集団の中の個人として考えてみる

私たちは産まれてすぐに、母親などと交流をしていることが観察されています(ビービー,B、ラックマン,F 2002)。私たちは産まれたときから人との関係の中で人生を送っているのです。このように私たちは人間関係の中で生きている、つまり個人と集団は切っても切れない関係と言えるでしょう。
ところで精神分析家ビオン,Wは、私たちのこころには健康的な側面と不健康な側面があると考えました。そして人が集まってできる集団にも、同じように健康的な集団(作動グループ)と不健康な集団(基底的想定グループ)に分かれると考えました(2016)。すなわち、私たち個人がストレスなく人と交わり仕事や勉強をスムーズに行えるこころの状態と同じように、職場や学校のクラスも和気あいあいと楽しい雰囲気に満ちている状態を作動グループと名づけました。一方で私たち個人がストレスで押しつぶされそうになって辛い状態と同じように、職場や学校がギスギスした雰囲気で生産的なことが行えない状態を基底的想定グループと名づけました。
このように私たち個人のこころには健康的な側面とそうでない側面があるように、集団も同じように健康的で生産的な状態(作動グループ)にある場合とそうでない状態(基底的想定グループ)があると考えられます。私たちが職場や学校という集団の中で嫌な思いをするとき、個人のこころがつらい状態であると同時に、それは集団が機能していない基底的想定グループの状態にあるとも言えるでしょう。
3 個人と集団をシステムとして考えてみる。

例えば職場で嫌な思いをしたとします。この時嫌な思いをさせた同僚に対して怒りが向くでしょう。これをシステムという視点で見てみましょう。
この職場はあまりマネジメントがうまくいっていないかもしれません。この同僚は仕事をしていくうえで、仕事上で感じている自分の不安を上司や職場が十分に抱えてくれているという実感が持てていないのでしょう。そうであるならばこの不安を本人は自分でもどうしようできなくなり、誰かへの攻撃という形でストレスを解消しようとしたと考えることができると思われます。
このようにシステムとして考えると、集団で何が起きていたかというメカニズムを俯瞰的に理解することができます。つまり集団が健康的でない状態(基底的想定集団)になっている原因をシステムとして考えるのです。加えて個人への怒りという抑えがたい感情を、システム上で何が起きているのかという理性的な分析によって、私たちの気持ちはずいぶんと楽になることでしょう。このように「個人の行動や経験の幅を決定づけているのはシステムであると認識することで、なんでも個人のせいにする閉鎖的な考えの影響から組織は解放され、変化への戦力を考案する新たな道が開かれる」と言えるでしょう。つまり「組織がどう動くかは、その組織で働いているいかなる個人よりも、その組織で発達してきたシステムに強く影響される(スーザン・ギャン/イヴォンヌ・アガザリアン 組織と個人を同時に助けるコンサルテーション 2018)」のです。
4 集団は上下のシステムで成立している
下記の図を見つつ検討していきましょう。一番大きい輪が会社とします。真ん中の輪が係・島とします。一番小さな輪は私たち個人です。
図 システム階層(「組織と個人を同時に助けるコンサルテーション」参照)

例えば同じ係の島で人間関係がギスギスし始めたとしましょう。この人間関係のギスギスさで同じ島の人たちは心がつらくなりストレスがたまります。このように真ん中の輪である島で起きたことは、真ん中の輪に接する小さな輪である個人に影響を与えるのです。同じように真ん中の輪である係の悪い雰囲気は、一番大きな輪である会社の影響を受けているのです。例えば会社が儲けだけを優先して人員を減らしたため、時間外労働や休日出勤が増え、とても忙しくなった。かつ成果主義によって同僚はライバルになってしまったという、一番大きな輪である会社の状況が、真ん中の輪である係のギスギスした雰囲気を作り出していると考えます。このように集団をシステムを考えた場合、図のように集団は大・中・小という階層によってシステム化されています。
同じように学校を生徒個人を一番小さな輪、クラスを真ん中の輪、学校を一番大きな輪として見ることもできます。すると生徒同士のトラブルをクラスや学校のシステムによって生じているという視点からも見ることができます。
このように、「システム階層によって、システムは文脈の中で観察されることになる―あるシステムは、その上位システムという文脈の下に存在すると同時に、その下位システムにとっての文脈として機能する中間システムとして存在していると(スーザン・ギャン/イヴォンヌ・アガザリアン 組織と個人を同時に助けるコンサルテーション 2018))説明されています。
そこで私たちは、個人のこころの健康の回復・維持に努めることはもちろんのこと、システムと見る考え方からは、システムがいかに健全に運営されるかという、集団の健全性・機能性の回復・維持という視点も、個人のこころの健康の回復・維持には大きな影響を与えています。その時真ん中の輪にある集団の健全性・機能性を回復・維持することに努めることが効率的だと言われています(前掲書)。なぜなら、真ん中の輪は大きい輪と小さい輪の両面に接しているため、真ん中輪のシステムの健全化が、大きい輪と小さい輪の両面でそれぞれのシステムに影響を及ぼすからです。ですから集団をシステムと考える視点からは、まず係・島の集団が健全的に機能するように働きかけることが重要になります。
5 個人の視点からと集団をシステムとして見る立場からのカウンセリング
当相談室では、私の産業分野や教育分野での経歴から、仕事や学校をお休みしている方への復職・登校支援としてのカウンセリングも行っています。その際、カウンセリングによって相談者のこころの健康を回復を支援するだけでなく、今回ご紹介した会社や学校をシステムとして考える視点から、復帰した後会社や学校というシステムのなかで、個人としてどのようにこころの健康を維持していくかという観点からもカウンセリングで支援しています。