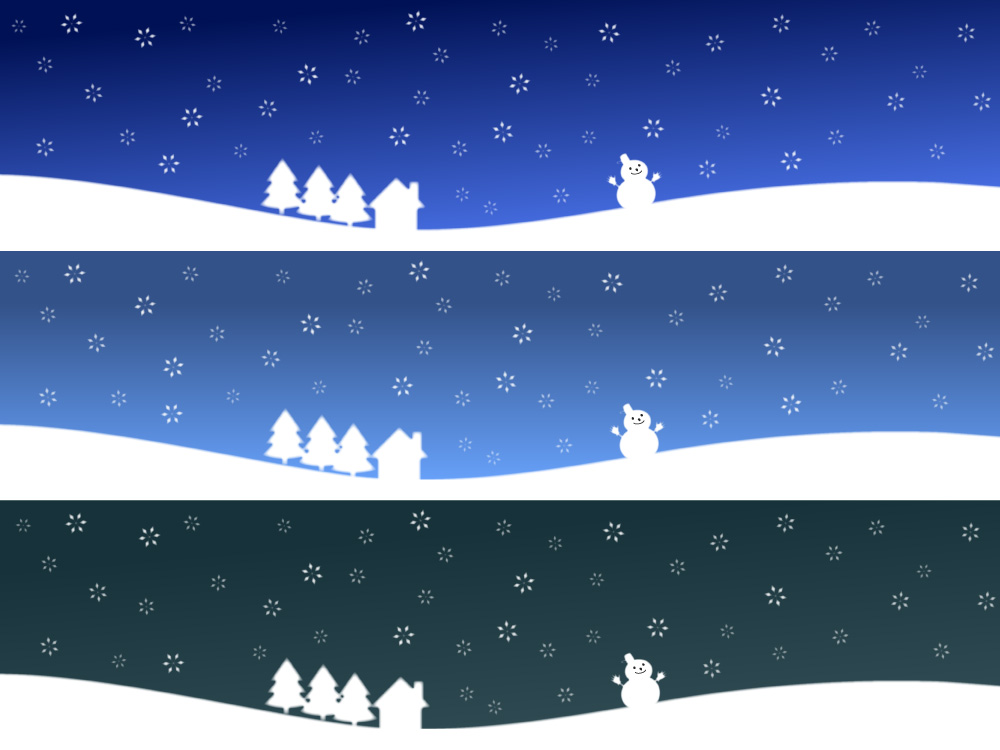戦争とトラウマ 「ルポ 戦争トラウマ 日本兵たちの心の傷にいま向き合う」を読んで
1 はじめに 私たちの身近にあるトラウマ
臨床心理士の勉強会などで、トラウマについて話題に上ることも多くあります。またカウンセリングでは、不安や苦しみを訴えられて、そのお話を伺っていくと虐待などのトラウマ体験のエピソードが語られることもあります。このようにトラウマ体験は私たちにとって身近な問題とも言えるでしょう。
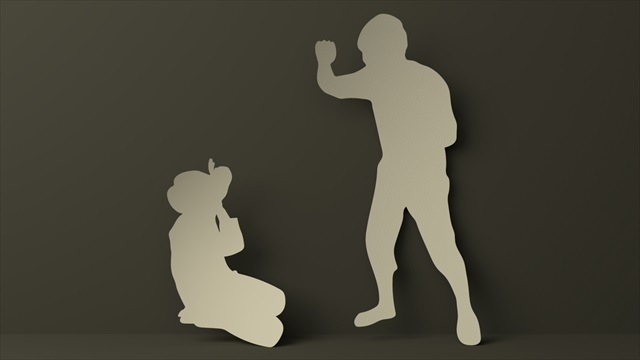
トラウマを体験すると、トラウマ反応といって様々な心身の症状が現れます。トラウマ反応はアメリカ精神医学会の診断基準ではPTSD(心的外傷後ストレス症)と診断されることもあります。そのPTSDが診断基準として加えられた背景として、ベトナム戦争の帰還兵が様々な症状によって社会に適応できないことが大きな社会問題になりました。「タクシードライバー」などの映画によっても描かれているほどです。このように社会的な関心が高まりましたが、ベトナム戦争以降も、アフガニスタン、イラクからウクライナ、ガザまで戦争が続いています。Five Finger Death Punchというバンドの 「Wrong Side Of Heaven」という曲のミュージックビデオでは、戦争帰還兵がホームレスに身をやつす危険が高いことを告発しているようです。アメリカではいまだに戦争とそれにかかわった人たちのトラウマの問題は現在進行形として認識されているのでしょう。
私もこれらの映画やビデオを観ましたが、戦争は遠い外国の出来事として観ていました。ところが「ルポ 戦争トラウマ 日本兵たちの心の傷にいま向き合う (朝日新書)」を読み、日本でも戦争によるトラウマが現在進行形で家庭の中で猛威を振るっているということに気が付かされました。
2 戦争のトラウマと家庭
前掲書に紹介されたトラウマの専門家も、家庭で経験されるトラウマと、戦争によって引き起こされるトラウマが関連していると気づくことが難しいと紹介されていました。例えば家庭で起きる虐待は、虐待をする親とそれを受けるこどもに生じる問題であると受け止められていました。しかし虐待を行う親は実は戦争から帰ってきたトラウマを抱えた自分の親から虐待を受けてきたというケースは多いのではないかという関連性が注目されるようになってきたそうです。こどもと親の間には子育てを通じて気持ちのつながり(愛着)が形作られます。しかし戦争を体験した親はトラウマ反応に悩まされ、こどもに愛情をもって接することができなくなります。そうした親子関係で育ったこどもは、自分が親になったときに、うまく自分のこどもに愛着を結ぶことができなくなる、トラウマが世代を超えて影響を与えていることになります。

塚本晋也監督の「野火」は戦争の過酷さや残虐さを表現していました。しかしあのような過酷な経験を戦後復員してから家族を含め日本の社会が共有することはありませんでした。それは終戦を挟んでそれまでの軍国主義から民主・平和主義に日本国民が一斉に方向転換した日本で、戦争のことを語ることは平和な未来に対する汚点になるということで、語ることを許されなかったということだそうです。語られないこころ傷=トラウマは、トラウマ反応として感情の爆発などとして家族に向かわざるを得なかったのでした。
第二次世界大戦で亡くなった日本人は約310万人と言われています。その何倍、何十倍の人たちが戦争による死を身近に経験したことでしょう。前掲書が指摘しているように、現在人々を苦しめているトラウマも元をたどれば戦争のトラウマにたどり着く確率は大きいのではないでしょうか?
3 他人のふりができない
画家香月泰男のシベリア抑留を主題にした絵は見るものにどうしようもない暗澹たる思いを湧き上がらせます。しかし美術館を出ればそのような暗澹たる気持ちからは解放されます。そうやって戦争は他人事して切り離されます。それは切り離さないと私たちのこころが辛くなりすぎるからだと思います。
しかし第二次世界大戦であまりに多くの人がトラウマを経験していることを考えると、私たちの肉親や親戚、知り合いのなかに誰か戦争のトラウマを抱えている人がいると考えることは自然ではないでしょうか?そのような身近な人たちが誰にも言えないトラウマを抱えており、そのトラウマが本人だけでなく、多くの人を苦しめていることから目を背けることはできないと思われます。
ところでヨーロッパの哲学者、エマニュエル・レヴィナスやジャック・ラカン等も戦争を経験しました。レヴィナスは、「今日でもなおアウシュヴィッツは超越論的観念論の文明によって犯された」と考えていました。ラカンに精神分析を教えてもらってたスチュアート・シュナイダーマンも、「西洋思想を賦活化させてきた主体性概念の転覆は、この計画(形而上学と神学の刷新)の第一部だった。第二部は<他者性>との対話あるいは弁証法であった」(内田樹 他者と死者から抜粋)と述べています。
難しい言い方ですが、私なりの理解を示してみたいと思います。西洋の考え方は、私が何かを理解するというものだと思われます。私が中心となって世界を理解していくというスタンスだと思います。世界で起きていることは科学によってすべてわかることができる。お金で欲しいものはすべて買うことができるという考えも、同じような考え方だと思われます。しかしレヴィナスやラカンは、この私が世界を理解できるという考え方が、第二次世界大戦の悲劇を生んだと考えるのです。考え方で戦争が起きる?そんなことがあるのか?と不思議に思われるでしょう。
私たちはご飯をいただくとき、「いただきます」「ごちそうさま」と言います。これは他の生き物の命をいただくという、他者の犠牲で私が成り立っているいうことへの感謝と、他の命を殺して食べることへの罪の意識があらわされていると思われます。しかしスーパーで買ってきた肉は綺麗に包装してあり、命ではなく商品として私たちは受け止めてはいないでしょうか?だからうっかり賞味期限を切らしてしまったときは、他の生き物の命に対する罪の意識よりも、何百円か損をしたとは考えていないでしょうか?
同じように現代の戦争では、人の命も、戦争で得られる利益と失われる損失をはかりにかけられているように思われます。そこには生身の人間の恐怖や悲しみ苦しさは忘れさられているようです。このように、私が世界を理解するという考え方は、すべてを私中心に考えるために、他の人たちの気持ちをおもんばかることができず、自分にとって都合が良いか?役に立つのか?という考え方に行きついてしまいます。それゆえこのような私が世界を理解するという考え方を変えない限り、世界から戦争などの悲劇はなくならないとレヴィナスやラカンは考えたのだと思います。
4 戦国大名たち
テレビの歴史番組を見ると戦国時代の大名が取り上げられています。それは戦争のトラウマを生み出す殺戮者としてではなく、英傑として取り上げています。また刀剣をキャラクターに模したコンテンツも人気と聞きます。このように私たちは戦国時代の戦争をした人や、使っていた武器に対してロマンさえ感じているようです。果たして戦国時代の戦にはトラウマを訴える人はいなかったのではないでしょうか?

江戸時代初期に書かれた沢庵の「不動知神妙録」には、刀を扱うことについての極意が書かれています。でもどうして臨済宗の僧である沢庵が、人を殺す方法である剣術について論じているのでしょうか?この書には、刀をうまく扱おうとこころがとらわれることを「住地煩悩」と呼び、これでは相手に切られてしまうと言っています。反対にこころをとらわれから解き放った状態を「石火之機」と呼んでいます。
レヴィナスは私が世界を理解しようとする姿勢が世界を戦争の悲劇に導いたと考えています。この考えは、私が刀をうまく扱う、自分の思うがままに刀をコントロールしたいという「住地煩悩」と同じ考えと言えるでしょう。そこで平和をもたらすためにレヴィナスは、世界を理解しようとする私を捨て去らなければいけないと考えたのだと理解しています。これをレヴィナスは「存在するのとは別の仕方」と呼びました。沢庵は、私から自由になる「石火之機」と同じではないかと言うかもしれません。このように沢庵の時代、剣術の修業をすることは如何に効率よく人を殺すために刀を扱えるようになるかではなく、私から如何に自由になるか?という禅に通じる悟りの境地に行きつくための修業であることが、社会的に共有されていたのだと思われます。そして私から自由になる悟り境地こそが、社会の平和を作ることを知っていたのかも知れません。
私たちはいつのころからか、私が世界を理解しコントロールしたいという「住地煩悩」にどっぷりとはまりきっています。そしてこの姿勢が戦争の悲劇を生んできました。戦争によるトラウマは他人ごとではないと書きました。それは確率として無視できないほど身近に起きているというニュアンスを含んでいると思われます。それはどこか戦争のトラウマに出会わなかった幸運の立場から眺めていると言えるかもしれません。しかしレヴィナスが指摘するように、戦争は私たち一人ひとりの心持から生じているように、私たちが戦争を引き起こし、これからも引き起こしていく、まさに私自身の避けることのできない問題と取り組む、待ったなしの問題であると言えるでしょう。それゆえ他人事ではなく、私の問題として取り組まなければいけないのです。
5 精神分析的心理療法における私
精神分析と今日のテーマ、戦争とトラウマとは一見無関係に思われるでしょう。しかし残念ながら精神分析も、私が、私のコントロールできない無意識をコントロールできるようになることが治療の目的と考えられてきました。沢庵の教えとは逆行する考え方です。ヨーロッパの哲学者ドゥルーズ=ガダリは「アンチ・オイディプス」で、この精神分析の態度を批判しましたが、精神分析の中でこの批判を受けて立った形跡は残念ながらないようです。
しかし精神分析家ビオンが、「欲望なく、記憶なく、理解なく」と主張したように、私が何かを理解しコントロールしようとすることを批判し、理解したいコントロールしたいという自分を捨て去るように促しました。沢庵が教えるように、私にとらわれることが生きづらさの原因になっているのならば、精神分析的心理療法においても、とらわれる私から如何に自由になれるのかをカウンセリングの目的にすべきだと当相談室でも考えます。

精神分析的心理療法は、可能性を開くとお伝えしましたが、それはとらわれた私から自由になることが、「石火之機」の境地に至ることであり、悟りを開くことと同じだと考えるからです。さらにレヴィナスの考えからは、私たちが精神分析的心理療法によって、とらわれた私から自由になることは、世界の平和を私たちの責任によって築きあげていく作業でもあると言えるでしょう。