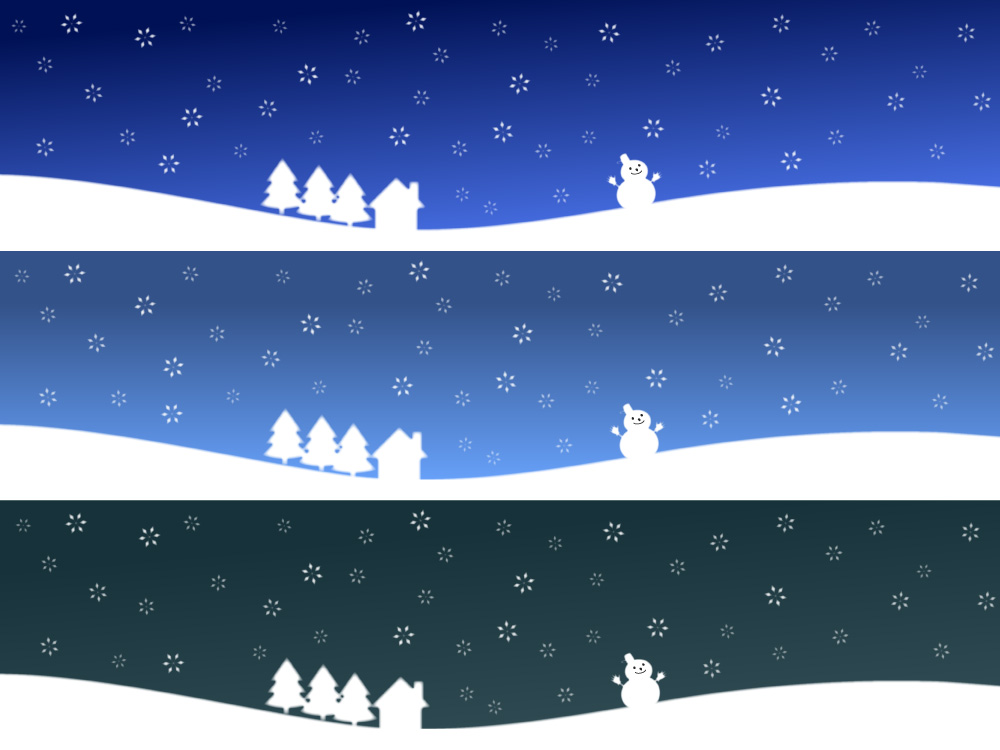ストレス対処と自己効力感 自分でものごとを決めることの大切さ
1 はじめに 予測できるストレスと予測できないストレス
今年の夏は暑すぎる日が続きました。毎朝天気予報を見るたびにうんざりさせられていました。いつまでも暑い暑いと思っていたらもう11月になり、上着を羽織る時期になりました。

ところで、「Couldn’t stand this weather」という、スティーヴィー・レイ・ヴォーンの曲があります。まさにうんざりするような今夏の天気を連想させる曲名です。しかし1984年に発表され、それまでのヒット曲とは全く違った、曲名とは反対に暑さを吹き飛ばすようなギター演奏に夢中になって聴いていました。
同じように天気に含まれる現象に台風と地震があります。台風と地震を比べた場合、現在台風はコンピューターによる解析で予想進路などを比較的正確に予測できます。その結果台風に対しては備えることができます。一方地震は風説が信じられるくらい予測が難しいものです。その結果地震の方が台風に比べて恐怖心を抱かせやすいと言われています。その理由は、結果を予測できるということがストレスの度合いを下げているからと言われているからです(中野敬子 2005)。
今回のブログは、予想できること、コントロールできることという視点から、それがどう自己効力感につながるかをストレスから考えていきたいと思います。
2 抗えないストレスに対する対処法
今年の夏はとにかく暑く、毎日が大変でした。しかしいくら暑くても自然現象なのでどうすることもできません。私たちはこのようなどうしようもできないことに対して強いストレスを感じます。

1)ここでストレスに対する対処法を紹介します。
①問題焦点型
ストレスを生んでいる原因に対して、その原因を解決しようと試みることでストレスを軽くするストレス対処法を言います。
②情動焦点型
ストレスを生んでいる原因を直截解決できない場合に、原因を解決するのではなく、原因となった出来事に対する意味づけを変えるなどのアプローチをすることで気持ちの安定を図る方法を言います。
このようにストレスの対処法は大きく分けて上記の2つがあると言われています。では自然のように変えたくても変えられないストレスに対しての対処法はどうしたらいいでしょか?変えたくても変えられないストレスには、①問題焦点型のストレス対処法は使えません。②の情動焦点型のストレス対処法を考えて行きましょう。
情動焦点型のストレス対処法には、例えば試験に失敗した時に、失敗したこと結果自体を変えることはできません。しかしその経験を「人生の糧にきっとなるはずだ」と、出来事に対する意味づけを別のものに変えることはできます。そうすることでモチベーションを高め、来年に向けて勉強しようという意欲を高めることができます。あるいはいったん試験のことは忘れて気分転換に趣味に没頭する方法もあるでしょう。さらには辛い気持ちを誰かに話して理解し共感されることでこころが癒されることもあります。
このように情動焦点型はストレスを生んでいる原因自体にはアプローチしません。しかし意味づけなどを変えることによって気持ちや感情を落ち着かせる効果があります。
2)抗えないストレスでも、もう一度コミットできるか?考えてみる。
天気はもう本当にどうしようもありません。しかし一見どうしようもないと思われても、ストレスを生んでいる原因にアプローチできる場合があるかどうか?もう一度確かめてみることも有効です。例えば前述の試験に失敗したという例の場合、野村監督の「勝ちに不思議の勝ちあり、負けに不思議の負けなし」との格言の通り、何が合格に足りなかったのかを分析して、弱点を克服するための取り組みをすることができます。
確かに今年の試験の結果を変えることはできません。しかしその試験の合格を目指すのなら、弱点を分析し、対策を立て、実際にやってみる。そして効果を検証し、足りないのであればその足りないものを分析し、新たな対策を実践してみる。このようなアプローチがストレスを軽くするために役立ちます。見方を変えることで、ストレスに対して問題焦点型のストレス対処法を用いることができることもあるのです。
3)臨機応変に対処法を選んで実行する
確かに情動焦点型のストレス対処法の中にはこころの安定をもたらすものもありあす。しかし考え込んでしまい、問題を解決するための行動をなかなか起こさないために問題解決が遅れ、ストレス状況を深刻化させてしまう場合もある(中野敬子 2005)と言われています。
ストレス対処にとって大事なことは、ストレスを生んでいる原因に対してどのようなアプローチができるのかということを考え、その原因に合わせて柔軟な対処法を試みることだと思います。
私も何度も経験がありますが、試験に落ちた時にすぐに来年に向けて対策を考える気には到底なりません。落ちた原因がたとえ自分の準備不足だとしても、誰かに愚痴を聞いてもらいたいものです。そのような時、まずは情動焦点型のストレス対処法の方が、気分を落ち着かせてくれます。しかし愚痴ってばかりでは来年の合格は難しいでしょう。例えば期限を区切って趣味で気晴らしをしてから、落ちた原因を分析して対策を立てる、問題焦点型のストレス対処方に移る方がいいでしょう。
2 自己効力感とストレス対処法
たまにスポーツ選手が自分の不甲斐ないパフォーマンスに腹を立ててロッカーなどを叩いたり蹴ったりしてケガをするニュースを耳にします。試合の結果を変えることができないという事実からもう自分には何もできないといういらだちを自分でコントロールできなかったのでしょう。確かに怒りを何かにぶつけることで一時的なストレスの発散になるかもしれません。しかし怒りをぶつけることは、自分ではストレスを生んだ原因に何もできないと感じることになってしまいます。私たちは何もできないとあきらめを何回も経験すると、「何をやってもどうせダメなんだ」とあきらめるようになります。これは「学習性無力感」と呼ばれています。

裏返せば、ストレスと感じることがあっても、そのストレスをなんとかできると思えるとストレスを感じにくくなります(中野敬子 2005)。このように自分が何かをすれば結果が変わるだろうと確信できることを「自己効力感」と呼んでいます。学習性無力感とは正反対の考え方です。
ストレッサー(ストレスを生む原因)に対しいろいろなコーピング方法(=ストレス対処法)を用いることにより、そのストレッサーの自分に対する影響を軽減することができる(Folkman 1984)と言われています。つまりストレス対処法をすることによって、感じているストレスをやわらげることでこころを苦しさから解放することができます。またストレス対処法を試みることで自分のこころを苦しさから解放できたと経験することになります。そうすると次にストレスを経験したときも、きっと対処法をうまく実践することで良い結果が生まれるだろうと確信することができます。さらにこの確信=自己効力感を得ることで、いつストレスに襲われるかという不安を抱いて生活することがなくなります。不安とは原因がなく心配になることです。原因がないため対処の施しようもありません。それゆえただただこころのエネルギーを使い、苦しむことになります。ストレス対処がうまくいったという確信(自己効力感)があれば、そのような不安によってこころのエネルギーが使われることを防ぐことができます。
3 自己効力感と新たな挑戦 自分でものごとを決めることの重要性
自己効力感を得ることの一番大きなメリットの一つは、なにか新しいことにチャレンジするときに、いろいろ困難なことはあるだろうけれども、今までの経験を活かして挑戦すればきっとうまくいくだろうと信じることができることかもしれません。
天気のように一見何もなすすべがないと感じることがあるかもしれません。しかし一見なすすべがないと感じても、そのようなときは情動焦点型のストレス対処法を試してみることがいいでしょう。この試してみることで感じていたストレスによるこころの苦しさを軽くすることができる経験が、自己効力感を身につけることになります。もちろん見方を変えることで問題焦点型のストレス対処法をためすことができるなら、さらに自己効力感を得ることになるでしょう。
カウンセリングも、話をする、話を聴いてもらうと言う点では情動焦点型のストレス対処法になります。そしてカウンセリングを受けることを決断すると言うことは、自分で何かをすることを自発的に決めることであり、カウンセリングで話し合ったことをもとにストレスに対して対処していくことで、こころの苦しさを解決していくことは、まさに自己効力感を得ることになります。
カウンセリングを受けることは、こころの苦しさからやむにやまれずに受けるというイメージがあるかもしれません。しかし受けるということを決めるのはご自身の判断なのです。ものごとを自発的・自主的に決め、その行動によって結果を変えることができるという視点で、ご自身の行動をとらえることはとても大事なことなのです。

当相談室では、「お試しカウンセリング」を用意しています。自己効力感を身につけるためにも、一度お試しいただけることを願っています。