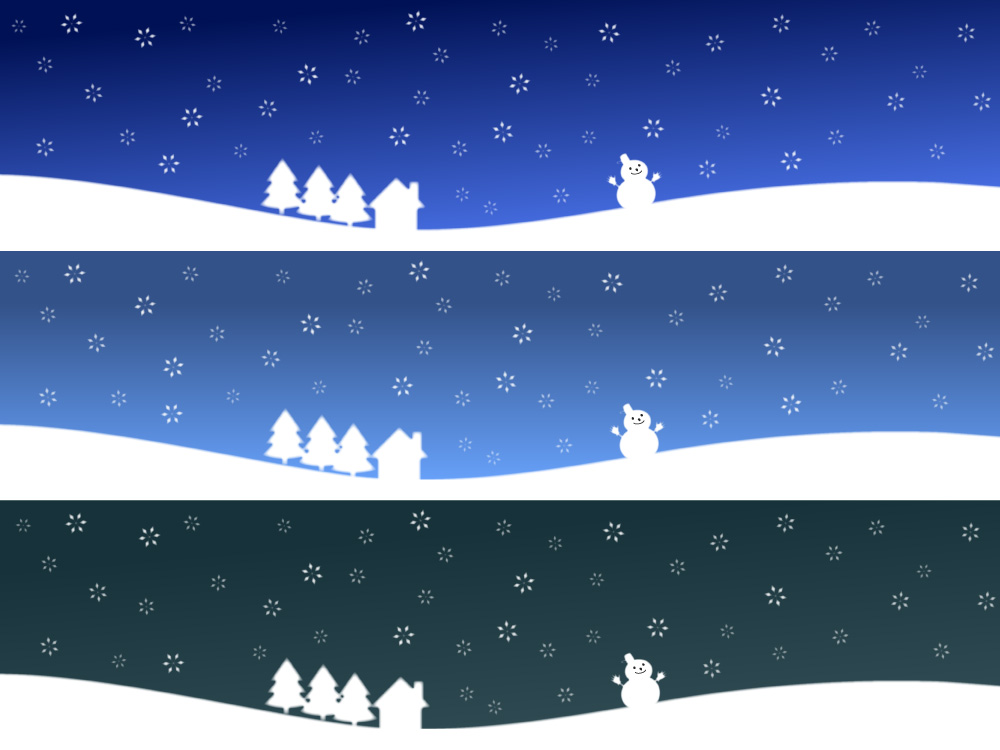食べることとこころの健康の関係性 精神分析的な考えかとそれに対する反論
9月に入っても猛暑が続くと食欲も落ちてきます。刺激もある味なら美味しくいただけるのではないか?と考え、今日の昼食はタイ料理にしました。タイ料理は辛味・酸味・塩味・甘味が混ざりあい、ハーブも効かせてあるので、おいしく食が進みました。

1 食べることは退化?
フロイトは心的エネルギーという考えを提唱しました。人間が産まれてから約1歳までは口を使って母乳を吸うことから、フロイトは口に心的エネルギーを向うと考えました。次に1歳を過ぎるとトイレットトレーニングのために心的エネルギーは肛門に向けられるようになるとフロイトは考えました。このように心的エネルギーはこころが成熟するに連れて向かっていく身体の場所が異なっていくとフロイトは考えました。
大人になってもストレスが大きくなると、私たちはいわゆる子ども返りのように、ストレスを口を使って発散する場合があると考えられています。裏を返せば、大人としての成熟したストレス対処法を取るスキルを持っていないがために、成熟していないこどものようなストレス発散法のスキルしか使えないという、こころの成熟度の評価にも使われるようになっています。食べることが好きで、食べることでストレスを発散させている私としては、このフロイトの考えに反論を述べたい気になります。
2 進化論とフロイト
フロイトが青年時代を過ごした時期、学問的にはダーウィンの「進化論」がドイツ語に翻訳され、ドイツに旋風を巻き起こしたそうです。フロイトもそのような時代のエートス(雰囲気)に触れ、また大学で師事した先生の影響によって、「進化論」から多くの影響を受けたと言われています((ダーウィンの進化論の現在 エルンスト・マイヤー 養老孟司訳 岩波書店 1994)。そのような中で考え出された心的エネルギーの向かう場所がこころの成熟度合いで変わっていくという考え方も進化論の影響を受けたとは考えられないでしょうか?
このような進化論的考えはフロイトだけでなく、現在の私たちにも知らず知らずの内に影響を与えていると思われます。例えば汲み取り式の便所と洋式のウオシュレット付きのトイレをどう評価するでしょうか?このように社会が過去から現在へと進化していくという考えと、進化した社会の方が先進的・文化的であるという評価は一体となっていると思われます。社会の教科書を読むと原始から始まって現在で終わります。何となく現在の進んだ科学・文化的社会から未開の原始の社会を振り返っているような気にはならないでしょうか?
3 循環するこころのあり様と垣根を作って行き来を拒むこころあり様

しかし果たしてそうでしょうか?文化人類学者レヴィ・ストロースは、いわゆる先進国のような日々変化している社会を「暑い社会」と呼び、狩猟採集のような社会にあって何百年と変化が少ない社会を「冷たい社会」と呼びました。「冷たい社会」はいつまでの汲み取り式の便所を臭くても使い続けます。しかしその溜まった排泄物は畑にまかれ作物を育てます。「冷たい社会」は自然と人間が作った人工物の間に垣根を作らず循環させる社会なのです。こころのあり様も同じです。縄文時代、人が亡くなると集落の真ん中に埋葬しました。生と死も垣根なく一続きに考えていたのでしょう。排泄物も身体の中にあった時は忌み嫌うことがなかったのに、ひとたび身体の外に出たとたんに臭いと忌み嫌います。身体の中と外を分けるように、現在の私たちの「暑い社会」は至るところに垣根を作って、お互いの世界を行き来できないようにしています。
4 異なる世界を行き来できる、疎通性の良さがこころの健康につながる
このように「暑い社会」に属する私たちが暮らす社会では、こころも、それに連動して社会も垣根を作ってお互い行き来できないようにしています。人間の細胞を作るたんぱく質は分子のレベルでは7日間で身体全体すべて入れ替わるそうです(福岡伸一)。この入れ替えが行われなくなれば人間は死んでしまうでしょう。このように本来は異なった領域を行き来することは生命にとって必須のように、こころにとっても行き来できることが必須なのです。
しかし私たちは自分のこころにとめ置けない、自分で認めがたいものをこころの奥底に沈めて見ぬふりをします。あるいは自分のこころから締め出して、なかったことにします。そうすると沈められたり、締め出されたものは本来は私たちのこころの一部であったものなのに、残った私たちのこころと行き来できなくなります。この状態がこころの健康を害すると精神分析では考えます。
当相談室で行うカウンセリング、特に精神分析的心理療法ではこのこころの垣根をとっぱらい疎通性をよくすることで、こころの健康を回復させることを目指します。
5 疎通性をよくする知恵
鈴木大拙「禅と精神分析」に、荘子天地編の撥釣瓶(はねつるべ)の話が紹介されいます。ある農夫が旧式の釣瓶を使って農作業していたところ、通りかかった旅人がもっと便利で楽な撥釣瓶をどうして使わないのかと訊きました。すると農夫は「こんな便利なものを使い慣れてくると、人間の心まで機械心になってしまうだろう」と、撥釣瓶を使わない理由を応えました。「冷たい社会」に住んでいた人たちは、「暑い社会」で当たり前のものが便利なことは知っていたのでしょう。しかし「暑い社会」のものを取り入れてしまったら、今自分たちが持っているあらゆる領域を行き来できるこころのあり様や社会が無くなってしまう。そうするとこころも病気になり、社会も荒廃してしまうと知っていたのでしょう。それゆえ古い進歩のないと「暑い社会」からみなされるものをあえて、こころと社会の健康を保つために使い続けたのでしょう。

そう考えると、童心に返って美味しいものを食べてストレスを発散させる私のストレス対処法も、「冷たい社会」の知恵につながっているのかもしれません?