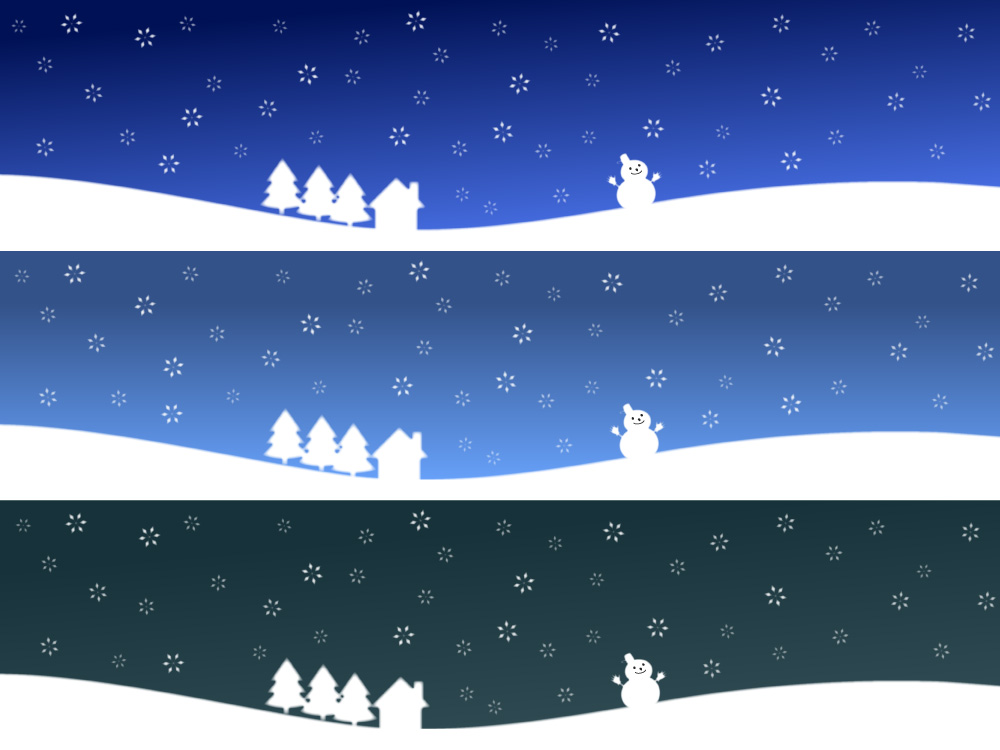精神分析的心理療法の到達する目標と創造性を発揮すること
「私」として主体的に生きることは当たり前だが、その当たり前の「私」によって私は苦しめられ、本来持っている創造性が発揮できなくさせられている。
1 はじめに
韓国ドラマにはまって、毎日観ています。韓国ドラマの魅力は、俳優の演技がとてもうまく、グイグイと引き込まれてしまうこと。また脚本も凝っていて、いろいろな工夫が凝らされており、飽きずに最後までのめり込んでしまうことです。最近は「私の夫と結婚して」を観ました。このドラマも俳優の演技と優れた脚本のおかげで最後まで楽しめました。嫌な役を演じている俳優を観ていると、本当に憎たらしく思えてくるほど、演技が真に迫っているのです。一方ドラマの主人公も自分の人生を取り戻すために、これでもかと迫真の演技を続けるため、観ている私としては、そこまでしなくてもととつい弱気に思ってしまうほどでした。

2 私、自分、我、自我を持つこと
ドラマの主人公はそれまで自分を押し殺し他人を優先してきたことを後悔します。そして主人公は私を取り戻し、私を強く主張し推し進めることで幸せをつかみます。つまり「私」という主体性を取り戻すことで人生を幸せなものにできるというメッセージがドラマから発せられます。このドラマだけでなく、「私らしく」といった主体性が人生にとって重要かつ大切であるという趣旨のメッセージはいろいろなところで見聞きします。
一方でこころの健康を害する、妬み、羨み、怒り、不安、恐れ。これら私たちにとってやっかいな感情も「私」があるからこそ感じるものです。私たちは「私」を持つことで、同時に仏教でいうところの煩悩としての、これらの厄介な感情も引き受けざるを得なくなりました。
このように「私」というものは、生きるうえで実に悩ましいものになってしまいました。
3 「わたし」をめぐる東洋と西洋の捉え方
鈴木大拙は「禅と精神分析」で東洋と西洋を対比させています。東洋の代表として芭蕉の俳句、「よく見れば薺(なずな)花咲く垣根かな」を紹介しています。一方西洋の代表としてテニスンという詩人の詩を紹介しています。その一部を抜粋しましょう。「もしわれ、汝のなんたるかを 根ぐるみ何もかも、一切すべてを知り得し時こそ われ神と人との何たるかを知らん」というものです。

鈴木大拙はテニスンの詩を、「知るということに強く訴えて行くところがとくに西洋的な特色を帯びている」「西洋はどうしてお言語性を好む・・・西洋は言葉を化して肉体化する」と評しています。「我思うゆえに我あり」というデカルトの言葉にあるように、西洋は私が言葉を使って考えることで、ものごとを理解すると捉えられているのだと思われます。このような捉え方では、言葉を使って理解する「私」と、「私」に理解されるものや相手といったように、わたしとあなたに二分されています。鈴木大拙はこれを「二元論」と呼び、これではものごとの本質を捉えられないと批判します。
一方で芭蕉の俳句は、「彼は言うべき言葉を知らぬのである。知らぬというのは、彼の感があまりにもきわまって、深くしてしかも深いということさえも覚えぬほどだから、これを概念に盛り上げようという気持ちすら起らぬのである」と評しています。東洋は言葉を使って考えることの及ばないところにものの本質はあり、西洋のように言葉の及ばないところにもかかわらず、無理やり言葉で考えようとすることをしないと、鈴木大拙は言っているのでしょう。
同じく鈴木大拙は、唐の禅匠、道吾禅師が弟子に「考えたらもはやそこにはない。考えるのではなく、じかに見て取れ。アレコレと思い迷ったり、頭で解釈するもんじゃないわい」という言葉を紹介しています。禅の目指すところも芭蕉の俳句と同じく、「私」が言葉を使って考えることができないところにある、ものごとの本質を、言葉を使わずいかにわかることができるか、これを追い求めることだと思われます。
つまり西洋はあくまで「私」を主体的な中心として、言葉を使って何でもかんでもわかろうしようとする。一方で東洋は「私」や言葉を超えたところにあるものを、わかろうとするものに一体となって感じることでことわりを体得しようとするものだと思います。
4 とは言っても「私」は言葉を使って考えてしまう。
私たちの脳は大まかにいえば、右半球と左半球に分かれています。左半球は意識や言語を司り、右半球は無意識の感情を司っていると言われています。そして私たちは産まれると右半球から発達させていきます。そして右半球が十分に機能する時期に、今度は遅れて発達した左半球が、それまで機能していた右半球を上書きすると言われています( A・N・ショア,2022 )。平たく言えば、右半球は左半球に乗っ取られてしまうのです。その結果私たちは常日頃から上書きされた左半球によって言葉で考えることを強いられていると言えるでしょう。ですから、左半球の機能によって自動的にものごとを言葉を使って考えるようになっていると言えるでしょう。
つまり左脳優位な私たちは、普段ものごとを芭蕉のようには捉えることが出来ずに、テニスンのように、「私」がものごとを言葉で捉えて理解しようとしているのです。
5 「私」を捨てるこころみ
確かに「私」が言葉を使って考えると、私たちはものごとの本質を捉えたかのように錯覚してしまいます。科学によって世の中のことわりがすべて明るみにてらしだされるように。
しかし鈴木大拙が言うように、「私」がものごとを言葉を使って考えても、それはものごとの本当の姿を理解することはできない。また「私」がものごとを言葉で捉えようとすると、前述のように、ものごとの本当の姿を捉えることができないばかりか、私たちのこころを悩ませる煩悩も連れてくることになります。
そこで東洋は、芭蕉のようにものごとを捉えることができるように、つまり「私」が言葉を使ってものごとを捉えないようにする工夫をしてきました。禅の修行もその一つの方法です。「禅と精神分析」のなかに、修行僧がいくら修行しても悟りが開けなかったところ、師匠がその修行僧を蹴り倒したところ、起き上がった修行僧は悟りの境地に達したという話が載っていました。このエピソードも「私」が言葉を使って考えることを捨て去ったところに悟りが開ける。つまりものごとの本質を知りたければ、「私」「言葉」「意識」を捨て去らなければならない。それが修行であると師匠は教えたのでしょう。
もう一つ興味深いエピソードを紹介しましょう。薩摩に伝わる剣術に示現流があります。ある日街中に野犬が出るというので、示現流の開始者の息子と弟子が野犬を退治しに行きました。首尾よく対峙した後、息子と弟子たちは刀を地面につかずに切ることができたという自分の技量を開始者の前で自慢しました。それを聞いた開始者は、切るとはこういうことだと、厚い碁盤を切り割り、刀はその下の畳を切り、その下の床材まで届いた言うことです。このエピソードも武道とは「私」が言葉を使って理解できるものではなく、「私」を捨て去った、言葉のつかえない世界に到達することであるということを開始者は息子と弟子に示したのだと、私は理解しています。
また「禅と精神分析」には渾沌の話も載っています。渾沌という神様は目も鼻も耳もなかったのですが、渾沌に接待された神様が、それでは不便だろうと接待のお礼として渾沌に目や鼻や耳になる穴を開けてあげました。すると渾沌は死んでしまったという話です。このエピソードも「私」が言葉を使って考えることはとても便利で一見分かった気にさせられます。しかしそれではものごとの本質を捉えられないばかりだけでなく、煩悩に悩まされてしまう。東洋ではこの「私」を持つことがいかに危ういものであるのかということを共通認識として持って今のでしょう。それゆえ「私」を捨て去ることを目的とした禅や武道、俳句、能などが高く評価されていると思われます。
6 精神分析的心理療法の目的
これまで当相談室で行う精神分析的心理療法を、根本的に問題を解決するカウンセリングであるとお伝えしてきました。どう根本的であるのかを、この「私」を捨てるという視点からご説明します。
精神分析的心理療法を続けていくと、精神分析家W,ビオンが提唱した「破局」という状態が起きると言われています。それは「破滅の恐怖といってよいような解体的な無統合が起きてくる強烈な感覚と不安を繰り返し体験する」 (松木邦裕 精神分析体験)と説明できます。ではなぜ「破局」が起きるのでしょうか?精神分析的心理療法を続けることで、それまでの「私」が言葉を使って、それまでの「私のこころ」を理解しようとしてきたことが出来なくなったことで生じると考えられます。つまりそれまでの「私」を捨て去らざるを得ない、「私」がない状態ゆえに生じる恐怖だと思われます。しかしそれまでの「私」を捨て去ることができたなら、「私」があるゆえに悩まされたことがらからも解放されるのです。「私たちが心的に一度死んでしまわないと、新しい考えを含んだ自己を構築できません。この心的な死が、破局です」(松木邦裕 精神分析体験)とも説明さらるように、破局を乗り越え先にそれまでとは違った世界を体験することになるのです。それはこれまでの言葉を使って考える「私」を捨て去り、言葉を超えた世界を体験するのだと思われます。この「破局」体験を仏教でいえば、「悟り」、「三昧」、沢庵和尚の「不動知」などいろいろな言葉で言われてきた境地と同じではないかと考えています。誤解を恐れずにいえば、精神分析的心理療法と他のカウンセリングとの違いは、精神分析的心理療法は言葉を使って考える「私」を捨て去り、かつての私とはまったく別の境地に至ることではないでしょうか?哲学者のレヴィナスの言葉を借りるなら、「存在するのとは別の仕方」に至ると言えるでしょう。

以前のブログで精神分析的心理療法は苦しみを解決するだけでなく、創造性を発揮するものであるとお伝えしました。鈴木大拙は、「生きるということの芸術家」になることと言っています。「生きることの芸術家などと言えば、どうも何か変にきこえるかもしれないが、実際のところ我々は皆、生きることの芸術家として生まれてきているわけである。ただ悲しいかな、我々のほとんどは、生きていることそのことが芸術であることを知らないので、生きていながら芸術家たりえず・・・」と言っています。私たちが「私」にこだわっている以上、生きることの芸術家にはなれない。「私」を捨て去ったときに私たちは自分が生きることの芸術家であることに気づくことができると言っているのでしょう。芸術と言われるものは、「私」が言葉を使って捉えることができないものを表現することを指すのだと私は考えています。いわゆる芸術家も「生きることの芸術家」も言葉を超えた領域を体験するという点では一緒だと思います。この言葉を超えた領域に「創造性」はあるのだと思います。この意味で精神分析的心理療法は創造性を発揮できると言えるでしょう。
精神分析家ナンシー・マックウイリアムズは、相談者から精神分析は科学なのかと訊かれ、「どちらかと言えば芸術」だと応えました。マックウイリアムズの意図も同じように、精神分析的心理療法が、「私」を捨てることでこれまでとは質的にまったく違った領域を体験すること、さらにはその領域に達することで、「生きる芸術家」となり、人間が持っていた本来の創造性を発揮できると考えていなのではないでしょうか?