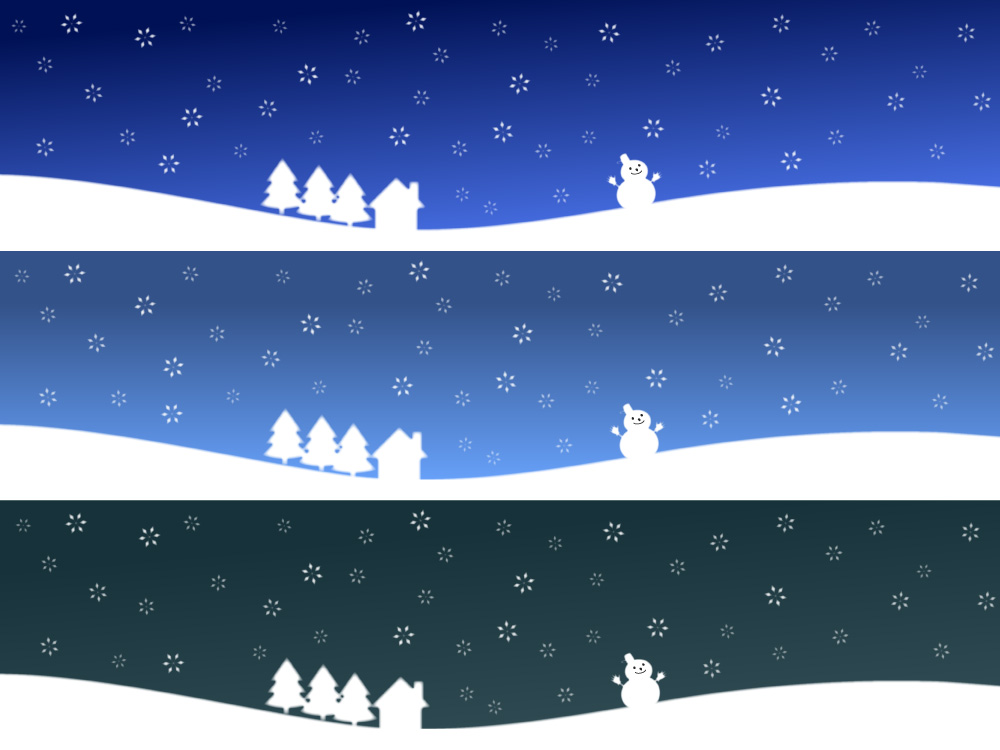幽霊と精神分析的心理療法 幽霊を怖がるメカニズムを精神分析的に考えてみる。
1 はじめに
暑すぎる日が続いています。カウンセリングルームの扉を開けると熱せられた空気が充満しています。このままでは観葉植物が枯れてしまうのでは?と心配になってきます。

さて夏になると涼を求めてか、夏は怪談の季節と思われているようです。私が小学生の時は昼時のテレビで恐怖体験を再現したドラマを放映しており、その放送を楽しみにしていました。いまでも毎年8月に幽霊画を公開している谷中の全生庵には何回か訪れています。夕方オレンジ色の西日が差し込む展示室に独り、床をギシギシいわせて幽霊画を見ていると、ぞくぞくしたものを感じました。
2 幽霊はなぜ怖い?精神分析的理解
縄文時代、人が亡くなると遺体は村の中央広場に埋葬されたそうです(松木武彦)。村の中央広場ではお祭りや生活の場であったので、生と死が全く別の世界に分断されているとは当時の人々は考えていなかったのでしょう。それが縄文後期になると村を離れて郊外に埋葬するようになったそうです。もしかすると、このころから生と死は切り離され、生と死は別の世界と考えられるようになったのかもしれません。
ところで「ハンスの症例」というフロイトの著作があります。5歳のハンスは馬をとても怖がりました。このことを聴いたフロイトは以下のように理解しました。ハンスの馬恐怖は、愛する母親を独り占めしたいために父親を亡き者にしたい。ハンスは馬に父親のイメージを重ね合わせており、ハンスにとって馬は父そのものとして受け止められていた。その馬=父親が倒れるところを見たハンスは、自分が願った父親の死が実現してしまったと考えた。一方で馬に噛まれることを恐れるハンスは、死を願った父親に母親を独り占めしたことで仕返しをされる恐怖をそこに見ていた、というものでした。この理解をフロイトは「エディプス・コンプレックス」と名づけました。
このフロイトの理解の当否は別として、私たちは身近な人に対して、親しさや感謝と同時に憎みもしているというアンビバレント(両価値的)な感情を持っているものです。それゆえ私たちも亡くなった人に対して、亡き人をしのぶ一方で憎しみや後悔も抱いています。それゆえ私たちもハンスと同じように、亡き人に対してのやましさから亡き人からなにかされるのではないかという恐れ、それがけがれの意識を生んでいるのではないでしょうか?
このような亡き人に向けた憎しみなどの感情が、亡き人からの仕返しをされるという心理が、死への恐怖を生んでいるのではないでしょうか?
3 世界を分けることで幽霊はもっと怖くなる

だいたい幽霊の出る場所はおどろおどろしい雰囲気の場所になっているようです。世間を騒がしている心霊スポットもそのような場所が多いようです。でも考えてみると私たちも必ず死ぬにもかかわらず、死んだ先に行き着く場所がおどろおどろしい場所となっているというのも納得ができないと考えるのは私だけでしょうか?
先に述べたように、私たちは生と死を分けてしまいました。死が怖いから分けたのか?分けたことで死が怖くなったのか?とにかく生と死が別れた現在、私たちが生きている生の世界から死の世界は全く隔絶された未知の世界となっています。私たちにとって知らないということはとても怖いことです。私たちが全く知ることのできない世界から恨みを抱いた死者がこちらに来ることは、私たちが死者に抱いているやましさから仕返しをされることに加えて、何か得体の知れない私たちには到底理解できないことに巻き込まれるのではないかという恐怖も抱くからなのだと思います。
4 分けて切り離しても、それは返ってくる
こころにとめ置くことができないものをこころにとめ置くとこころがあまりにつらいので、私たちはこころの奥底にとめ置くことができないものを沈めてしまっていると、フロイトは考えました。しかしいくら沈めていても何かの拍子に沈めていたものはこころに帰ってきます。この時私たちのこころは恐怖や不安でとてもざわつきます。これをフロイトは「抑圧されたものの回帰」と名づけました。
精神分析家メラニー・クラインは、こころが健康でない状態では、私たちは自分にとって良いことと悪いことを分け、悪いことは自分のこころにとめ置けないので、自分のこころから締め出してしまうと考えました。嫌なことが起きたとき、私たちは「あいつのせいで!」とつい怒りを覚えてしまいます。これは怒りという自分のこころにとめ置くことができない気持ちを締め出して、その気持ちを他の人のせい(投影)にしているからです。そして「あいつのせいで!」という、あいつからの不快な思いは、実は私の怒りが相手に投影されたもの、つまり相手の怒りと思っていたものは自分の怒りであったとクラインは考えました。
私たちが幽霊を怖がるのも、私たちが死者に抱くやましさを死者に投影しているからかもしれません。つまり幽霊が怖いのでなく、自分のやましさに自分で怖がっているのかもしれません。まさに「幽霊の正体見たり枯れ尾花」です。
5 こころの健康と幽霊
私たちは、自分で認めがたいこころにとめ置くことができない感情を、こころの奥底に沈めたり、あるいは他に人に投影します。しかしそれらが自分に帰って来た時に、私たちはそれらを自分の感情とは気づかずに、誰かからの悪意を向けられていると勘違いしてしまっています。そうすると自分のこころを正しく理解することができなくなってしまします。健康なこころとは、自分のこころがどうなっているのかを正しく理解できると言えるのかもしれません。正しく自分のこころの状態を理解できたときに、私たちは良い感情も悪い感情も、様々な感情を自分のものとしてとめ置くことができるようになることが必要と考えます。つまりこころを切り分けずにすべての感情を受け容れることができるようになります。こころが健康な状態とは、どんな感情も自分の気持ちとしてこころにとどめ置くことができる状態と言うことができます。この状態を目指すことが精神分析的心理療法の目的の一つでもあります。
ただ私たちは死の恐怖を幽霊に投影していますが、怪談などに死の恐怖を置き換えることで、死の恐怖が私たちに戻ってくる際の怖さをなかば楽しみに代えているとも言えます。怖さを楽しみに変えるというのも健康なこころの機能と考えらます。しかしその前提として、怖いものは怖いと素直に認めることが必要です。怖いと認めることができた先に、怪談のように怖さを楽しむことができると言えるでしょう。