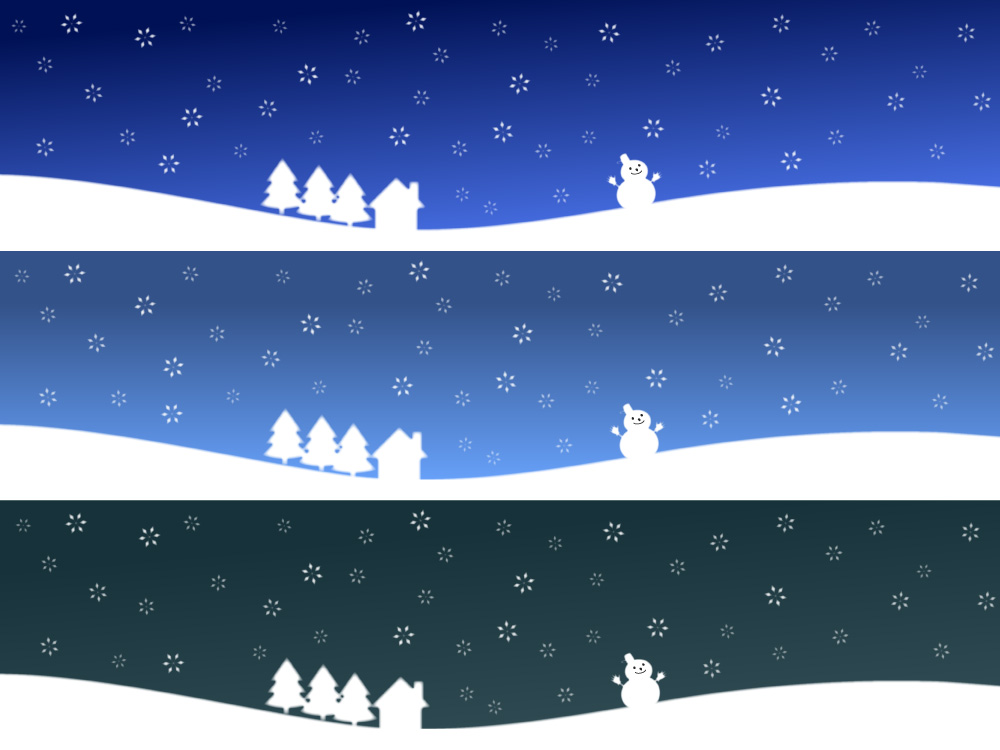カウンセリングを受けることで、自分だけではなく世界を変えることができるのだろうか?こころと社会の関係を考える。
1 はじめに
東欧や中東における戦争が伝えられるたびに、暗澹たる気持ちにさせられます。 これほどまで科学や文化が発展した現代においても、古代から延々と続く戦争を人類は止めることができません。
ところでカウンセリングとは、今まで気が付かなった自分を見つけることでこころの健康を回復させるだけでなく、抑え込まれていた創造性も発揮できるようになると当相談室では考えています。
ではカウンセリングを受けることでこころの健康を回復し、創造性を発揮できるようになることは、私たち個人だけのことであり、私たち自身以外の人たちに影響を及ぼすことはないのでしょうか?
今回は私たちのこころと私たちが生活する社会との関係について考えていきたいと思います。 私たちの内側と外側のとの関係を考えていきましょう。
2 こころは産まれたときから外部とコミュニケーションを取っている。
赤ちゃんは産まれた時から(最近ではお腹の中にいる時から)、言葉はしゃべれないけれどもお母さんと濃密なコミュニケーションを取っています(ビービーとラックマン 乳児研究と成人の精神分析 参照)。 コミュニケーションですからこの交流には気持ちのやり取りも含まれています。 赤ちゃんを中心に見れば、赤ちゃんは様々な気持ちをお母さんのこころの中に投げ込み、お母さんは赤ちゃんの気持ちを受け取って共感し、その共感を赤ちゃんのこころに返します。 このように私たちは産まれた時から自分のこころを使って自分の外とやり取りをしているのです(精神分析の用語では、投影と取り入れと呼んでいます)。 つまり私たちは産まれたときからこころを介して社会とやり取りをしているのです。 こころと社会は切っても切れない関係と言えるでしょう。
3、私とあなたとのコミュニケーション
上記の赤ちゃんとお母さんのコミュニケーションは、精神分析的心理療法においてクライエント(相談者)とセラピストとのコミュニケーションのモデルとなっています。 すなわちクライエントは苦しさや不安をセラピストに伝え、セラピストはそれらの感情を受け取って共感としてクライエントに返すというものです(コンテイナー/コンテインドモデル)。
このようなやり取りはカウンセリングの中だけではなく、日ごろのやり取りでも行われています。 例えば学校で先生に相談するとき、職場で上司や同僚に相談するとき、親に相談するとき、誰かにグチを聞いてもらうときなど。
もっともコミュニケーションのあり方はなかなか難しいと哲学者のエマニュエル・レヴィナスは言っています。 なぜなら私にとって「あなた」は全くの別人であるゆえに、私と何もかも違う「あなた」を理解することは至難の業だからです。 ではどうするかというと、私たちは自分のの基準で相手を判断しようとします。 私の考えではこうだから、きっと相手も私と同じように考えているに違いないと、私に当てはめて考えてしまいます。 このようなコミュニケーションのやり方をレヴィナスは過激な喩えで、相手を殺して食べると表現しています。 相手を理解するのではなく、自分勝手に相手をわかっていると思い込んでいることを。 このような表現で痛烈に批判しているのです。
これは精神分析的心理療法においても残念ながらあてはまるのです。 セラピストも自分の理解が全く及ばない他者としてのクライエントを目の前にしたときに、わからないということに耐えらないときがあります。 その時「これはこの理論からこう理解できる」「以前にこう言ってたから今回もきっとそうに違いない」「そんなはずはない、きっとこういうことだ」など、クライエントの気持ちを真正面から受け止めないで、自分の土俵で理解した気になって安心したいという誘惑にかられます。
このような誘惑にかられないで、わからないということに耐えて、クライエントの気持ちを正面から受け止める重要性を、精神分析家W・R・ビオンは「負の能力」として提案しました。 私もカウンセリングにおいては、分からないことに耐えることをいつも肝に銘じています。
哲学者レヴィナスも精神分析家ビオンも、自分が理解できない他者を、理解できないからといって自分の土俵に上げてわかった気になることをいさめたのでした。
最近相談した相手が「まあまあ、考えすぎっだって」と返すテレビのCMがありました。 どうして人の相談に乗れないのか? 私たちはわからないということがとても怖いのです。 相手の相談の内容が自分が理解できないほど深刻だったらと考えると誰でも怖くなります。 この怖さから逃れわかったと安心したい誘惑はとても強いのです。
4、社会の仕組みをコミュニケーションで考えてみると
柄谷行人(力と交換様式)は、どのように相手とやり取りをするかで世の中の仕組みを説明できると言っています。 そしてこのやり取りを交換様式と名付け、以下のパターンがあると言います。
交換様式A:誰かにプレゼントする、それに対してお返しをするパターン。 交換様式B:国ができて、国は色々なものを支配した人々から奪うけれども、安心して暮らせるように色々なこともやってくれる。 交換様式:C 何とでも交換できるお金を使うことで、自由にものとものを交換することができる。 というものです。 この交換様式、つまりコミュニケーションのやり方が変わることで社会の在り方も変わってきたと、柄谷は考えています。
私たちが誰かからプレゼントをもらったとき、うれしい気持ちの一方でこのお返しに何を送ったらいいか、ちょっとわずらわしく思うことはありませんか? 交換様式Aでは、もの自体を受け取った以外に、お返しをしなければいけないというわずらわしい気持ちも一緒に背負うことになります。 交換様式Aでは物と物とのやり取りに気持ちが大きくのしかかってくるのです。
一方でお金を使うなら、お金さえ払えば気持ちのわずらわしさからは解放されます。 この意味で、お金はなんでも解決できると言えるでしょう。 なんにでもわずらわしさを感じることがなく手にいれられることができる「お金」はなんと便利なものなのでしょう。
5、こころと社会の在り方をコミュニケーションから考える
私たちはわずらわしさを感じずなんでも手に入れたいという誘惑に負けて、お金を使うようになったともいえるでしょう。 この誘惑はこころとこころのコミュニケーションでも同じでしょう。 わからないという怖さに耐えることができない私たちは、私がこう思うんだから相手もそうだろうと、「私の考え」を相手に当てはめて、本当は分からない相手もわかった気にさせる誘惑にかられています。 どんなわからない相手もわかった気にさせる「私の考え」は、なんでも交換できる「お金」と同じ働きをしていると思われます。 そして両方とも、知らない怖さやわずらわしい気持ちからも解き放ってくれます。
先に書いたように、私たちは自分たちのこころのあり様を外に映し出しています(投影)。 わからない怖さに負けてなんでも「私の考え」で相手をわかった気にしたいというこころのあり様は、わずらわしい気持ちを持たずに自由にものを手に入れることができる「お金」を使うという社会の仕組みに反映しているとは言えないでしょうか? なんでもお金で解決し、人情味がないと言われる現代社会は、私たちのこころのあり様が反映されたものと言えるでしょう。 もっといえば世知辛い世の中にしているのは、私たちのこころが作り上げていると言っても言い過ぎではないでしょう。

4、自分の心を知ることで社会を変えることができる?
柄谷は交換様式Cが行き詰った現代において、この状況を打ち壊すために、これまでにない交換様式Dが現れるのを期待しています。 しかし現在の社会のあり様は、私たちが気持ちを伝え受け取ることを怖がりわすらわしいと思うことで表れていると考えるならば、交換様式Dは私たちのこころが変わらなければ現れることはないと思われます。
先に紹介したレヴィナスは、相手を私の基準で判断しないコミュニケーションの方法を「存在するとは別の仕方」と呼んでいます。 私たちは自分が理解できない相手のこころに恐怖を感じるために、自分基準で相手をわかった気になっています。 ですから私たちが自分基準ではなく「存在するとは別の仕方」で相手とコミュニケーションするためには、自分が理解できないという恐怖に耐える必要があります。
ところでカウンセリングでは、自分のこころを考える時苦しくなることがあります。 これは自分のこころであっても、自分のこころから締め出している自分が気づかない気持ちは、自分にとって他人のような存在だからです。 ですから自分の知らない自分を知るということは、自分が理解できないという恐怖にぶち当たります。 それでカウンセリングが苦しくなるのです。 しかしこの苦しさにセラピストと耐えることで私たちは新たな自分に出会うことができるのです。
このように知らないという恐怖に耐えて新しい自分に出会う体験は、私とコミュニケーションを取る相手にも同じようにふるまうことができるでしょう。 そうすれば私たちはお金に頼ることなく、気持ちと気持ちを通じ合わせる大切さに気付く、新しい社会が現れるのではないでしょうか? 社会がどのように変わって行くのか? それは私たちがどのように自分のこころに気づいていけるのかにかかっていると言えるでしょう