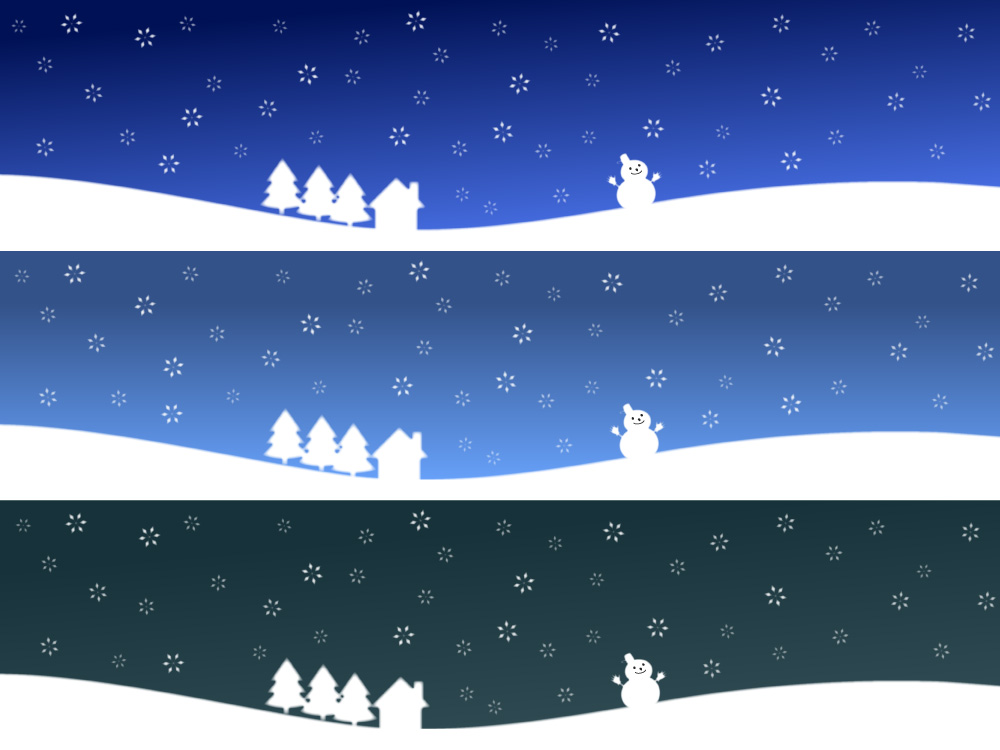問題を解決するためのカウンセリング 「共感」が人を変える
1、はじめに
私事で恐縮ですが、たとえば勉強会の資料を作らなければいけないとき、書くべきことはイメージできるのですが、なかなか取り掛かれません。どんどん先延ばしていき、今度の休みで書かないと後がない状況になっています。しかしその休みの日も「どうしても書けない」。ちょっと横になってからやろうと先延ばし、夕食を食べてからやろうと先延ばしし、もうこれ以上先延ばしできないという時間になってやっと書き始めるパターンばかりです。
子どものころのように宿題を出せなくて怒られることはありません。しかしあらかじめ余裕をもって書いた資料の方が概ね出来はよいため、さっさと取り組めるようになりたいものです。

2、すぐ行動できるようになるには?
今度こそ早めに取り掛かろう!と強い気持ちで望んでも、やっぱり次の日には「嫌々やっても良いものにならないし」と言い訳をして、やっぱりだらだらしてしまいます。こういう時自分のことは棚に上げて「本当に人間の気分はあてにならないな」としみじみ思います。
私が病院や復職支援で働いていた時、認知行動療法で用いるコラム表を書いてもらうことがありました。出来事をどう受け止めるかによって気分が変わるという人の性質を利用して、気分の受け止め方を変える練習をするものです。例えば何をやっても失敗するという信念を持っていた場合、その信念に矛盾する出来事を「反論」として考えてもらいます。この「反論」のポイントは、「事実」を思い出すことです。なぜ事実かというと、「そう思った」という気持ちは先の私の例のようにその時々で簡単にゆらいでしまうので、全く考え方を変えるには頼ることができないからです。一方で事実は気持ちと違っていつでも変わらないため、事実を頼りに考えれば信念を変えることができるからです。
ではさっさと行動に移すために、頼ることができない気もちに変わって、私は何を頼りにしたらいいでしょうか?
私はなぜさっさと行動に移せないのか?もう少し考えてみたいと思います。その理由を考えてみると、良いものを作りたいという気持ちに突き当たります。でも簡単に良いものはできません。あーでもないこーでもないと思いを巡らせているうちに、良いものができないプレッシャーに負けて取り掛かれないということがどうもありそうです。
ところで私が受けた研修で「子ども問題行動を解決する3ステップ ロス・W・グリーン 井上裕紀+竹村文訳 日本評論社」という本を紹介されました。訳者が講師だったこともあるでしょう。しかし私は訳者の講師の支援に対する熱意を感じ、この先生が興味を持って訳したのならきっといい本だろうと購入しました。
この本の特徴は、問題行動を起こす子どもは、そのことが悪いことでやってはいけないことをわかっている。わかっているのに罰を与えても意味がない。問題行動を繰り返してしまうのは、どうすればいいのかという「方法」を知らないからだというものです。
この本の主張を私の例に当てはめてみましょう。私がさっさと書き出せないのは、書き出すための「方法」を知らないからだと考えてみます。もっと掘り下げてみると、良いものを書こうとする「理想」に私の書く技術という「現実」が追いついていないからだと思います。そうすると、現実にすり寄って、私の書く技術に合わせるのがいいと思われます。例えば、まずは箇条書きでいいから書いてみる。書いてみればそこからアイデアが広がって来て、最後まで書ききれるかもしれません。私に足りていなかった「方法」は、簡単でいいからまず書き出してみることだったのかも知れません。
気合ではどうにもならない私でしたが、このように「方法」という現実的な対処法なら、すぐに書くことを始められそうです。

3、「方法」を実践するコツ したい行動の前の状況を把握する
それではどうやって「方法」を実践すればいいでしょうか?また私の例で検討してみましょう。
資料を作る時、時間がある休日にしようと思います。しかし休日家にいると色々しなければいけないこともありますし、第一書くということから逃げるための誘惑があちこちになります。気が乗らないから取り合えずパソコンで映画をみるかといった感じで。
すなわち書くという行動に至るためには、書くという行動を引き起こさせる、書く前の状況がとても大切になります。例えば受験生をゲームや漫画本であふれている部屋を与えておいて、「どうして勉強しないんだ」と怒っても、勉強するという行動を起こさせることにはつながらないのです。私の場合も、だらだらと自室にこもらず、朝ご飯を食べたら図書館の自習室に行かなければ書くことはできないでしょう。
せっかく「方法」が見つかってもその方法を実行するには、実行するもう一つ前の状況がどうなっているのかを調べることになります。
4、行動を変えるには「共感」が必要
この「方法」を実践するために、やりたい行動のもう一つ先の状況を理解することが大事とお伝えしました。先に紹介した「子ども問題行動を解決する3ステップ」では、この一つ先の状況を理解する過程を「共感のステップ」と書かれていました。そして大人は子どもが問題行為を起こしたとき、どうしてその問題行為を子どもが起こしたかを理解するために、丁寧に子どもに訊きながら状況を理解しなければならないと書いてありました。それは問題行動を変えるための「方法」を見つけるには丁寧に状況を理解する必要があるからです。
しかしあえて「共感」という言葉を著者が使ったのは意味があると考えます。この本に書かれている子どもたちはいつも頭ごなしに「なぜやらないんだ!」など、一方的に大人に責められてきました。そのような子どもたちに、その行動を起こしたのにはこういう理由があったのだと丁寧に耳を傾けてくれる大人がいると体験することは大きな喜びであるでしょう。
人が今までできなかった行動をできるようになるためには、もちろん客観的な状況分析をして効果的な方法で実践することが必要です。しかしながら私が「子ども問題行動を解決する3ステップ」を買おうと思ったのは、紹介した講師の熱意に感動したからです。このように人が何かしようと動きだす理由は、自分の気持ちが突き動かされ、それによって行動が変わるのだと思います。
これはカウンセリングでも全く同じだと思います。今困っていることや不安な心持ちをよくするために、同じように原因を探り、対処法を考えなければなりません。しかしその時に相談者が体験している気持ちをカウンセラーが寄り添ってわが身のように体験する、「共感」があるからこそ、相談者は良くなるための行動を起こすのだと考えます。まさに人は人との関係性で良くなって行くのでしょう。