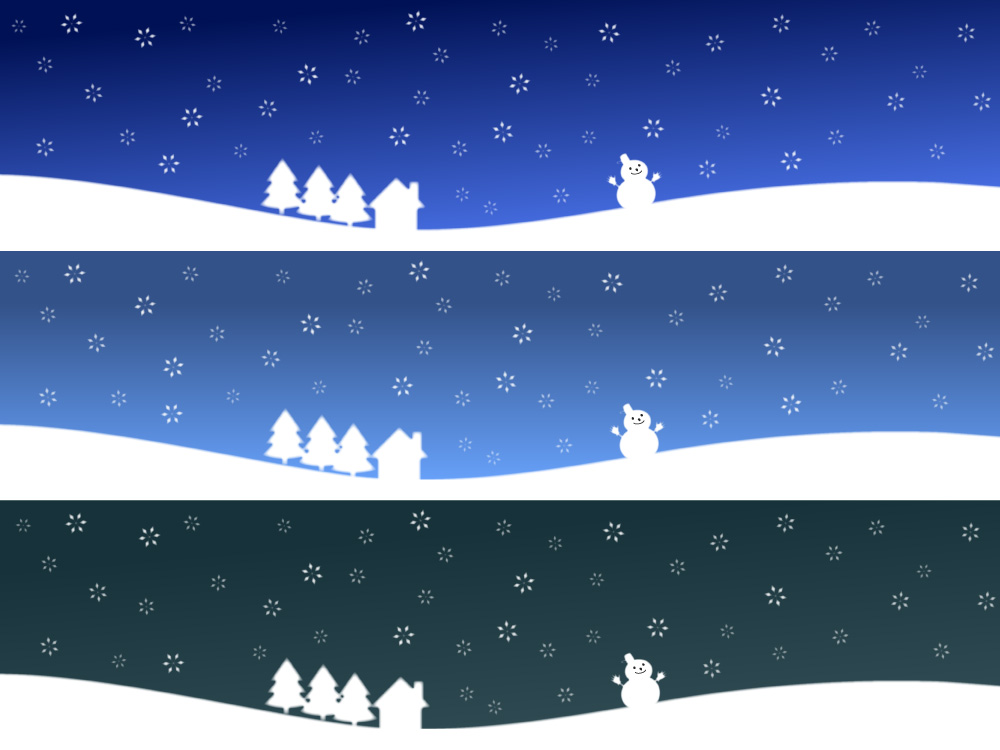人のこころは複雑、ゆえにカウンセラーはこころの問題もこころ以外の、その方の背景を見なければならない。相談者をカウンセリング・ルームだけでなく、その方の生き方として様々な方向から見るカウンセリング。
人のこころは複雑、ゆえにカウンセラーはこころの問題もこころ以外の、その方の背景を見なければならない。相談者をカウンセリング・ルームだけでなく、その方の生き方として様々な方向から見るカウンセリング。
1、はじめに
カウンセラーの経歴で、教育、医療、福祉、産業で働いてきたことを書きました。このブログでは、私の他方面での経験がカウンセリングでどのように役立つのか、また相談者の支援につながるのかをお話しします。
当相談室のカウンセリングは相談者にお会いして話を傾聴し、苦しみなど気持ちを共有したうえで、相談者が抱えている問題の解決を目指すものです。それゆえカウンセリング・ルームのみで相談者にお会いしているため、カウンセラーはカウンセリング・ルームの相談者しか知ることができません。
ところで「役割取得(GH ミード)」という考えもあります。人はその立場・状況に応じて振舞などを変えていくというものです。例えば、卒業して何十年経っても学生の時の友達と飲むと、その当時に舞い戻り、当時と同じように馬鹿話に花が咲きます。いい気分になって家庭に帰ると子どもが宿題をしていません。すると馬鹿話をしていた学生気分から一転、父親として説教をしてしまいます。あくる日会社に出勤して困っている部下を見ると面倒見のいい先輩として相談に乗っています。
過去、大相撲で横綱に昇進するとき、「地位が人を作る」と言われたことがありました。このように人は相手の関係性で生じる立場に応じて、それにふさわしい振舞をします。人はそれぞれの立場に応じて様々な顔を見せるものなのです。
2、カウンセリング・ルームでの相談者の役割
相談者がカウンセリング・ルームに来られるのは、今抱えている苦しみを解決したいと望まれるように、何かしらの困ったことがあるからだと思われます。そうするとカウンセリングを行うカウンセラーと困ったことを解決したい相談者という関係で、相談者はふるまうことになります。同じようにカウンセラーも相談者の困ったことを解決しようと注目します。そえゆえカウンセラーも相談者も、相談者の困ったことに着目することになります。そしてどうして困っているのかと原因を探し、どうすればよくなるのかと対処法を考えていきます。たとえるなら、お腹が痛いと受診した時、医者も患者も悪いところが何かに着目してどうすれば治療できるかという関係性に似ています。

3、カウンセリングルーム以外の役割取得
職場では?
このような相談者がカウンセリングを受けた翌日、会社に出勤したと想定しましょう。すなわちカウンセリング・ルーム以外の場面での役割取得がどうなっているのかも想像してみましょう。
もしその方が時間給を取ってカウンセリングを受けていたなら、翌日に出勤すると同じ島の同僚は心配して声をかけてくれるかもしれません。すなわち職場の人間関係をどう築き上げているのかという観点も必要になります。良い人間関係を築ける方だった場合、仕事を休んだ時も周りは心配してくれ、休んだ間の仕事も代わりにこなしてくれている(問題解決型ストレスコーピング)かも知れません。また仕事に復帰した後、もし気持ちが辛くなった時も相談に乗ってもらえるでしょう(情動焦点型ストレスコーピング)。視点を職場にまで広げるとその相談者が持っているストレス対処法の強みをカウンセリングの見立ての中に入れることができます。

学校では?
次に、同じように架空のケースですが、学校に通っている生徒さんが知能検査(WISC)を持って相談に来られた時を想定してみましょう。この生徒さんは先生の指示が良く聞き取れずに授業で何をしていいか分からないことで困っているとします。そしてそのことで度々注意を受けていることですっかり自信を無くしている様子がカウンセリング・ルームで伺えます。
WISCの結果からは目で見てどこに何があるのかを理解する力(知覚推理)、目で見た情報をから出来事の流れを(原因⇒結果)の読む力が平均であると出ています。生徒さんに家庭での様子を訊くと、家族で色々形のピースを見本通りに並べていくゲームに熱中していると教えてくれました。そしてその生徒さんは家族で僕が一番強いんだと嬉しそうに話してくれます。少し専門的な話になりますが、この目から入る情報(視覚情報)には、数字などのそれ自体に意味を持たないもの(無意味刺激)と漢字や漫画など視覚情報に意味が付いているもの(有意味刺激)、それに無意味刺激と有意味刺激が混ざったピクトグラム(トイレの表示や非常口の表示)のようなもの、の3種類があります。例えばパズルのピースが単に色が塗ってあるだけのものなら、相談に来られた生徒さんは無意味刺激を理解する力がWISCの結果より得意ではないだろうか?という推測を立てることができます。
もし家庭でのパズルの話から視覚情報の無意味刺激の理解が強いとの推測できるなら、学校での生活の一日の流れを図にして、家庭や担任と確認してから一日の学校生活をスタートする対処法ができるかもしれません。また完成すると風景が現れるパズルも同じように得意なら、無意味刺激と有意味刺激が混ざったものも得意と推測できます。そうならば学校での一日の流れを示す図に、体育の前の着替えを促すために体操着の絵を入れることも役立つと思われます。
このような対処法によって効果がみられ、学校で先生に注意されることなく楽しく過ごすことができるなら、この生徒さんの自己効力感も上がることでしょう。自己効力感とは、自分が何かをすれば結果を変えることができることを信じることができるという確信です。カウンセリング・ルームだけの役割取得だけでなく、学校での立場まで考えることで、学校での過ごし方だけでなく自己効力感も上げることができるでしょう。
4、さまざまな役割取得をイメージするカウンセリング
このようにカウンセリングでは、カウンセリング・ルームで会う相談者の印象だけではなく、その方が、職場で、学校で、家庭で、あるいは習いごとのサークル(サードプレイス)などではどのような役割を得て、どのように生活しているかをセラピストが想像することが大切になります。なぜならこころの不調はこころだけの問題として扱うだけでは良くなりません。その方のこころを健康に保つ力、人と良い関係を築く力、自己効力感、ストレスの対処能力、その年齢で求められる課題など多くの要因がかかわっているからです。そのためにはカウンセラーがカウンセリング・ルームだけでなく幅広い現場で働くことで、カウンセリング・ルームで座っている相談者の背景に広がる様々な役割をイメージできることが必要であると考えています。