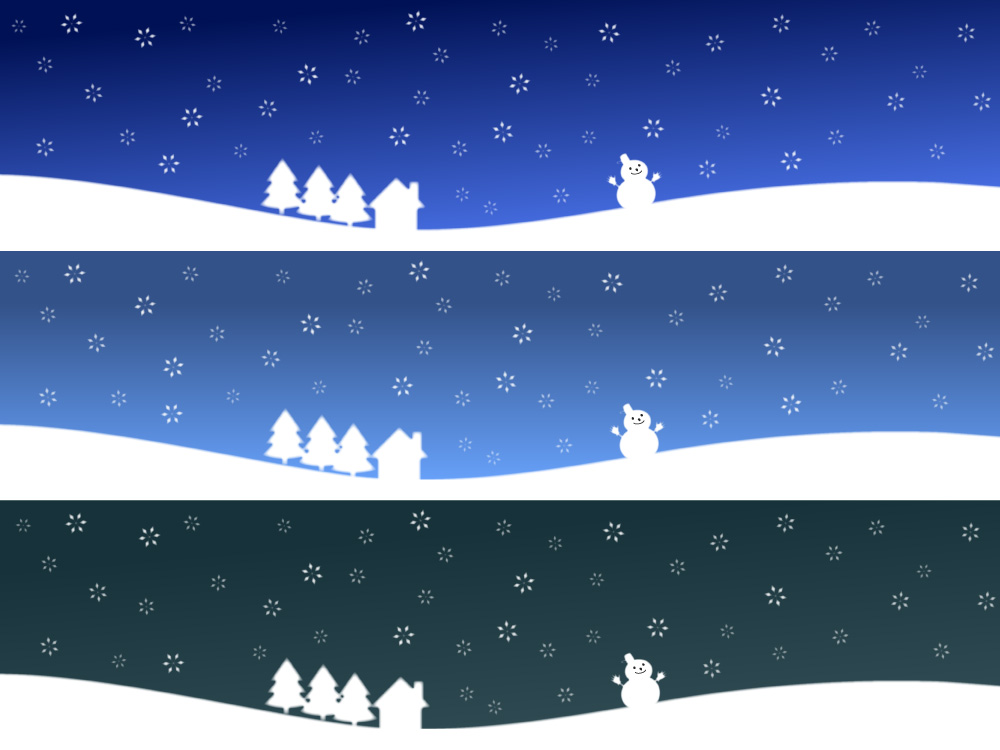カウンセリングでこころが成長するとはどういうこだろうか? エリクソンの漸成的発達理論から考える
カウンセリングでこころが成長するとはどういうことだろうか?
エリクソンの漸成的発達理論から考える
1、はじめに
カウンセリングを希望されるとき、この辛い状況を抜け出し、将来同じような状況に陥っても乗り越えられる術を身につけたいと思っていらっしゃる方も多いと思われます。カウンセリングを受けることで「こころの成長」を期待されているからだと考えています。
確かに辛いことに出会ってもそれを乗り越えることができるという実感をカウンセリングで身につけることは「こころの成長」にとって大事な要素になります。このような何かをすればきっと状況が変わるだろうという実感(自己効力感)を持つことで、新しい人生の可能性を信じてチャレンジすることができからです。
ただ「常に」こころが成長すると捉えると逆に息苦しくなる時はないでしょうか?昔から禍福はあざなえる縄のごとしと言われています。うまくいかない時に自分のこころが成長していないからだと捉えるのは、逆にストレスをためてしまうことになり、こころの健康に悪影響を及ぼしかねません。
2、エリック・エリクソンの漸成的発達理論

エリクソンは人間のある時期にはその時期特有の発達に関する課題と同時に危機も体験すると言います。しかし課題と危機のせめぎ合いを乗り越えるとそこに成長への力を得ることができるとも説明しています。
例えば、赤ちゃんは自分一人では生きて行くことができません。おなかがすいて泣けばお母さんがおっぱいをあげ、おむつが汚れて泣けばお母さんがかえてくれる。このように世話をされることで赤ちゃんは人に対する「基本的信頼感」が生まれてきます。一方でお母さんはいくら赤ちゃんのことを想っていても、100%赤ちゃんの要求に応えることができません。おなかがすいて泣いてもすぐにお母さんが来てくれないこともあります。このようなとき赤ちゃんは「不信感」を持つようになります(このような状態を心理社会的危機と呼びます)。しかし不信感をいだいても、やっぱりお母さんは自分を愛してくれているんだという実感を赤ちゃんが持つことができれば、不信感に基本的信頼感が勝り、「希望」という力を持つことができるとエリクソンは考えました。
このようにエリクソンは人生のそれぞれの時期で、それぞれの心理的課題と心理社会的危機のせめぎ合いを乗り越えることで、こころを成長させ生き抜く力を得ることができると考えました。
3、ダーウィンの進化論がいたるところに影響している?
さきほどのエリクソンの発達理論は、「漸成的」という名前がついています。この「漸成的」という意味は、人のこころが産まれてからゆっくり分化して成長していくというものです。
この「ゆっくり分化して成長する」という考え方は、おそらくダーウィンの進化論に影響されていると思われます(ルーシール・B・リトヴォ ダーウィンを読むフロイト 青土社 参照)。原始的な生物からゆっくりと分化し高等な生物に進化してきたという考え方を、こころの成長に重ね合わせたのでしょう。
ところで歴史の教科書を見ると石器を使っていた時代から始まって、本は今に近い現代で終わっています。私たちは歴史対しても、文化も技術も最高点に達している「今」という高みから、原始的な生活からゆっくりと分化し現代に進歩してきたと見ていないでしょうか?
また経済を見ても、物々交換の時代から資本主義に発達していったと、同じように原始的からゆっくりと高度な経済活動に進化していったと受け止められています。
私たちはこころの成長だけではなく、社会制度や技術、文化も、生物と同じようにゆっくりと進歩しているはずだと信じているようです。
4、死ぬまで進化論に影響されている?
エリクソンの発達論は「老年期」まで説明しています。その後に私たちは生物として避けられない死を迎えることになります。精神科医キューブラー・ロスは、私たちが死に直面した時に①衝撃②否認③怒り④取引⑤抑うつ⑥受容の過程を経て、死を受け入れることができると主張しています。例えば自分は死ぬかもしれないと知らされた時、①相当のショックを受けます。②自分がそんな運命にあるわけがないと事実を受け容れることができません。③それでも事実が変わらないと、どうして自分だけが死ぬ運命にあるのだと怒りが湧きます。④怒りが尽き果てる時、例えば、神様によいことをする代わりに生かしてくださいと取引をします。⑤最終的には死から逃れられない事実の前に打ちひしがれますが、最後には死を受け入れる、という過程をたどると言われています。
キュブラー・ロスの考えはみずからが死にゆく過程ですが、一方で自分にとって大切な人を亡くす、あるいは大切なものを失う時(対象喪失)も、同じような過程(喪の作業)をたどると主張されています(ボウルビィ J)。すなわち①情緒危機②抗議③断念④離脱という過程をたどると言われています。例えば、試験に落ちた時、①落ちたショックで現実を受け入れることができず、気分は落ち込みます。②あれだけ頑張ったのにどうして落ちたんだと、落とした方に間違えがあるんじゃないかと怒りも湧いてきます。③それでも落ちた事実が変わらないとなると、あきらめ、無気力などがこころを占めます。④最後に落ちた事実を認め、来年の試験に向けて頑張ろうという意欲が芽生えてきます。
これらの意見も死や喪失を受け入れるという目標に向かってゆっくりとこころが整っていくという、進化論をなぞっているような見解です。
ただこれらの意見には、必ずしもこのような順番をたどらないし、行きつ戻りつしながら進むものだという反対意見もあります。
5、禍福はあざなえる縄のごとし
このように私たちは知らず知らずのうちに過去より現在の方が良くなっているに違いないと思い込まされているとは言えないでしょうか?
確かに自分が何かをすれば結果が変わるという自己肯定感を身につけることは大事なことです。でも頑張ってもどうしようもないときもあります。そのようなときに良くならない、前に進めない自分はダメだと捉えるのは、人間のこころのあり方を正しく反映していないと思います。また正しくない理解はこころの健康にとっても良くありません。
思想家内田樹は、甲子園の予選に何千校と出場するのに優勝するのは一校のみ。なのになぜみんな勝つことを当然の前提にしているのか?優勝する確率は何千分の一なのだから、負けることを前提として対処する方が現実的ではないか?との趣旨を書いていました。禍福はあざなえる縄のごとしで、私たちの生活もいいこともあれば悪いこともあります。決して前に進むことだけがすべてということはありません。
心理学では「プラトー現象」という考えがあります。例えば勉強を同じペースで頑張っていたのに、ある時から勉強しても結果が出なくなったということが起きると言われています。これまで右肩上がりに成績が上がっていたのに、同じように勉強しても成績が伸びない状況を「プラトー(踊り場)現象」と呼んでいます。この時進化論に影響を受けている私たちは前に進まない状況に不安を覚えてしまいます。しかし踊り場(プラトー)と呼ばれるように前進はしていませんが、この踊り場を過ぎればまた成績は上がってきます。このように何かを身につけるという時にも、前に進むだけではなく、停滞と前進を繰り返しながら結果的には前に進むという過程をたどります。
6、こころの成長とは?
私たちのこころはこれまで見てきたように直線的に右肩上がりに成長・進歩するわけではありません。精神分析家ビオンはこころには健康な側面とそうでない側面が振り子のように入れ替わると考えました。この考えの上に精神分析家ロナルド・ブリトンは、健康的な側面とそうでない側面が振り子のように入れ替わったときに、以前の状態からバージョンアップしていると考えました。一見同じ繰り返しに見えてもそこに何らかの成長への変化があるということなのでしょう。生物学者福岡伸一よると、人間を形作っているたんぱく質は約七日間ですべて入れ替わるそうです。人間はこころも身体も変化を繰り返しながら少しずつバージョンアップをしているのでしょう。ただバージョンアップなので右肩上がりのような派手な成長を実感できないことで、「プラトー=踊り場」のように感じ、成長していないとやきもきしてしまうのでしょう。しかしこころの成長とは、はっきりした成長を実感できないときでも、とどまることなく変化すること、その動きを止めないことで徐々に変化すると考えられます。

7、当相談室の取り組み
当相談室のカウンセリングでは、今感じている苦しさや不安にセラピストも向き合い、さらに将来の出来事に対しても対処できるよう支援し、自己効力感を身につけられるように付き添います。
ただ人生もカウンセリングも一見前に進んでいないと感じるプラトー=踊り場に差し掛かる時があります。そのようなとき、成長していないという焦りや不安にも丁寧に寄り添い、こころがとどこおらないように支援します。そして一見何の成長もないと感じられるなかに本人も気づかないバージョンアップした変化を丁寧にフィードバックしていきます。