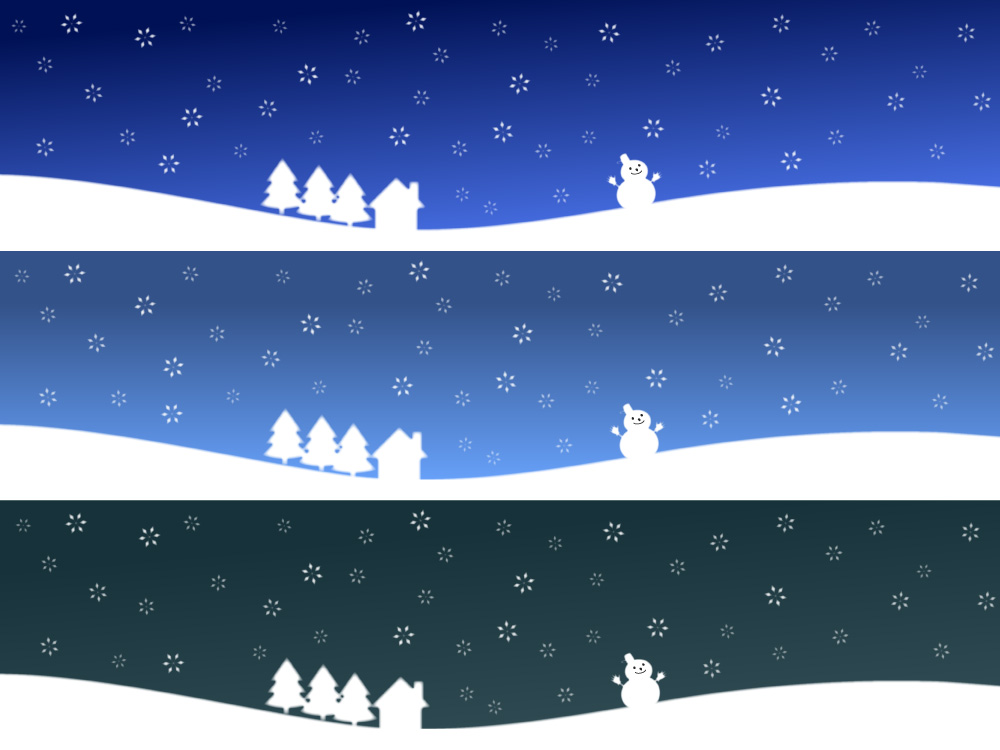認められたい気持ちと傷つきたくない気持ちの狭間 人と人との距離感を自己愛の観点から考える。
1 はじめに
ずいぶん前から人と人との関係が希薄になったと言われています。実際に職場の飲み会に行きたくない人はアンケート全体の約73.6%にのぼり、その理由として「気をつかう」が92%になっています(Can Can.jp)。気をつかうとは、おそらく相手とどう距離をとって接していいか分からないために、人とコミュニケーションを取ることを避けている人が多くなったということでしょうか?今回のブログは、「自己愛」の観点から、人と人との距離感を考えていきます。
2 自己愛とは?
精神分析では、他者から良い評価をもらうことで自尊心が高められることをとても気にしていることを「自己愛(ナルシシズム)」と呼んでいます。「われわれの誇りは重要な他者から是認されると高められるし、是認されないと傷つけられる(ナンシー・マックウイリアムズ,2005)」ように、私たちは大なり小なり他者からの評価、すなわち褒められればこころは元気つけられ、逆にけなされればしょんぼりすることを経験しています。それゆえ私たちは他者からいい評価をもらいたいと、仕事や勉強を頑張るということがあります。適度な自己愛は、植物が日光を浴びて成長するように、仕事や学業を充実させるものです。
ところで私が最近熱心に観ている韓国ドラマ、たとえば「ミセン」や「ライブ」では、新人が自分の能力が及ばずプライドが傷つき落ち込むものの、仲間や先輩に支えられ壁を乗り越えていく様子が上手に描かれています。他者からの評価を求めても自分の実力不足からそれをもらえないために傷つくもの、それでも挑戦していく様子は健全な自己愛の在り方の見本のようです。他方で人と人との距離を取る日本では、自己愛が傷つくことを恐れて行動に移せないし、その傷つきを癒してくれる仲間も見つけられない状況なのかも知れません。
では私たちは他者からの評価を気にしなくなっているのでしょうか?そうではないでしょう。自己愛の傷つきを恐れるということは、他者からの評価が欲しいのに傷つくことが怖くて欲しいと言えない、つまり他者からの評価を切実に願っている点は変わりありません。しかしあまりに他者からの評価を気にしすぎることは、いろいろとこころの健康にとっては問題が起きることになります。

ナルシシズムという言葉は、フロイトがギリシャ神話のナルキッソスから名づけました。ナルキッソスは同じ言葉ばかり繰り返すエコーに愛想を尽かして見捨てたように、またカラバッジョの絵にあるように水鏡に映る自分しか愛することができなくなったように、自己愛が強くなると、人は他者からどう評価されるかにだけに気を取られて、それ以外のことに関心を向けることができなくなります。自分を評価してくれるかどうかだけで他者を価値つけてしまうような対人関係に陥ってしまいます。極端な言い方になりますが、高価なブランド品を持っているから自分が評価されていると錯覚するように、他者は自分の評価を上げてくれる「物」のように扱ってしまうこともあります。自己愛の弊害の一つは、人からの評価を切実に望んでいるのに、人ととの間に温かい交流ができずに孤独に陥るパラドックスが生じることにあります。
3 自己愛のタイプ
他者からの評価を求めるやり方には2種類あると言われています。一つは「俺ってすごいでしょ」とあからさまにアピールするタイプがあります。もう一つは、あからさまにアピールすることはなく、どちらかといえば控えめにふるまっているものの内心では人からの評価を切実に願っているタイプです。前者は「厚皮の自己愛」あるいは「無関心型」と名づけられ、後者は「薄皮の自己愛」あるいは「過敏型」と名づけられています。しかし「どんなに虚栄心が強い誇大的な自己愛者にも人目を気にする恥ずかしがり屋の子どもが隠れているし、またどんなに抑うつ的で自己批判的な自己愛者にも自分がどんな人間でなくてはならないか、またどんな人間でありうるかについての誇大的な理想像が隠れている(前掲、マックウイリアムズ)」というように、私たちは、「どう?すごいでしょ!」とアピールしたくなる時もあれば、「認めてほしいけど、そう言ったら傷つく言葉が返ってきそうだから」と言いたい気持ちを押さえつけるときの両方を体験してると思われます。
4 「させていただく」表現にみる自己愛
「させていただく」という表現を、椎名美智の「させていただくの使い方(角川新書 2022)」で見てみましょう。「させていただく」は関西地方が起源であり、昭和30年代に東京でも使われるようになったという説があるそうです。そして1990年代に使用頻度が高ります。「戦後の日本社会は、人の上下関係を重視する縦社会から、人々の繋がりを重視する横社会へと変わりました」「私たちの敬語使用が動作主や動作の向かう相手に対して敬意を示す従来の伝統的な敬語から、コミュニケーションの相手、つまり聴き手を意識して、自分が丁寧に話していることを示すタイプの敬語へと傾いてきている」というように、敬語は人と人との関係性を反映するもので、社会関係が変化すると敬語の種類や使われ方も使われ方も変化します。「させていただきます」もこの社会の変化に連動して盛んに使われるようになったようです。
ではどうして「させていただく」は盛んに使われるようになったのでしょうか?同書には、就職が決まった学生が決まっていない学生に遠慮して、就職が決まったことを発表しないことが紹介されていました。就職が決まったということを声高に話すと、妬みや反感を買うのではないかと控えているのでしょう。これは私たちの日常でもよく経験する心性だと思われます。つまり私たちは本当はおめでとうと祝って欲しいけど、それを言ったらどう反応されるのかを気にしている「過敏型」あるいは「薄皮の自己愛」の心性におおわれているのでしょう。その点「『させていただく』を使うと、話し手と聞き手は近づきすぎず遠ざかりすぎず、絶妙の距離感を保ってコミュニケーションができるのです。このつかず離れずの距離感は、現代社会に暮らす私たちが心地よいと感じる他者との関係性や距離感にぴったり合っています」というように、誰かから評価して欲しいという自己愛を満たしつつ、誰かから妬まれ攻撃されて傷つくことを防ぐという点ではとても使い勝手はよいからでしょう。
一方で昨今承認欲求を得るためのSNSの使用も話題になっていますが、これは「厚皮の自己愛」あるいは「無関心型」の自己愛のパターンに当てはまると思われます。
このように現在私たちは誰かに評価してもらいたいという欲求を何らかの形で求めている時代の中で生活しているといるでしょう。いわば自己愛の時代に巻き込まれていると言えるでしょう。
5 自己愛の時代を生きるにあたって
前述のように誰かからの評価ばかりを気にしていると、結局は孤独になってしまうということが自己愛の最も大きな問題点であると言えるでしょう。一方でG・H ミードが説くように、私たちはコミュニケーションによって他者に支えられることで、私という存在を実感できます。つまり他者からの評価や承認は私が私であるために必須の栄養源と言えます。つまり自己愛は栄養でもあり、それが過ぎると孤独という毒にもなるものなのです。

では私たちはこの自己愛とどう付き合っていけばいいのでしょうか?前述の韓国ドラマでは、自己愛の傷つきを同僚や上司のかかわりや励ましの中で癒しています。つまり私たちは仲間によって自己愛を傷つけられる一方で、その傷つきは仲間でなければ癒されないと言えるでしょう。私たち人間はコミュニケーションの生き物なのです。
このような自己愛の時代で生きる私たちは、学校でも職場でもあるいは家庭でも、人と人との関係が生じるところで、他者からの評価に苦しむことがあるでしょう。もし他者からの評価に苦しんでいらっしゃるならば、カウンセリングというコミュニケーション方法を利用することで、ご自身の自己愛の問題を解決することを考えられることもきっと役立つと思います。